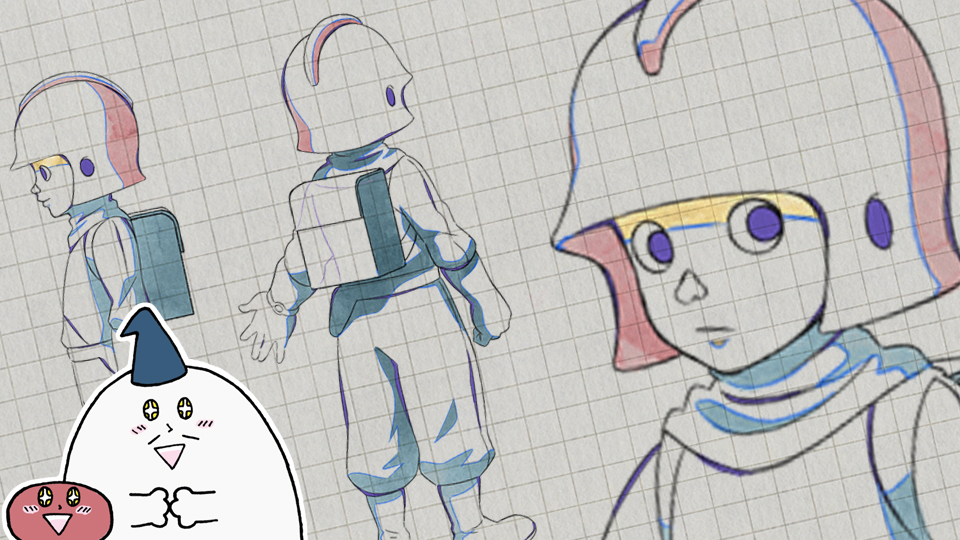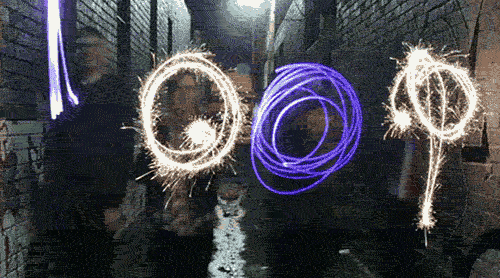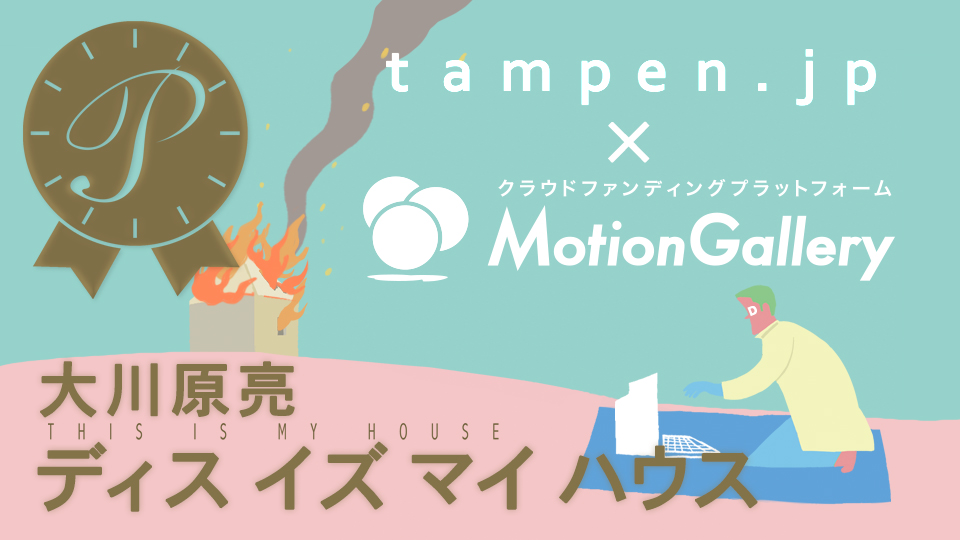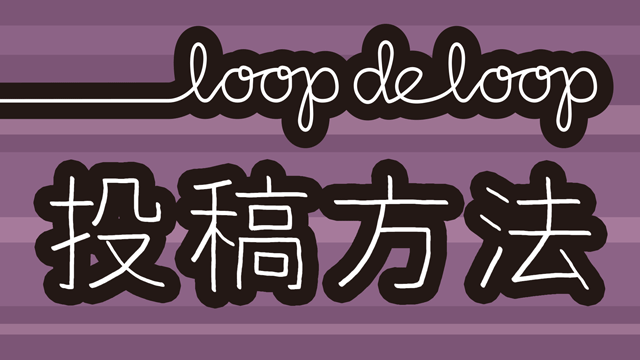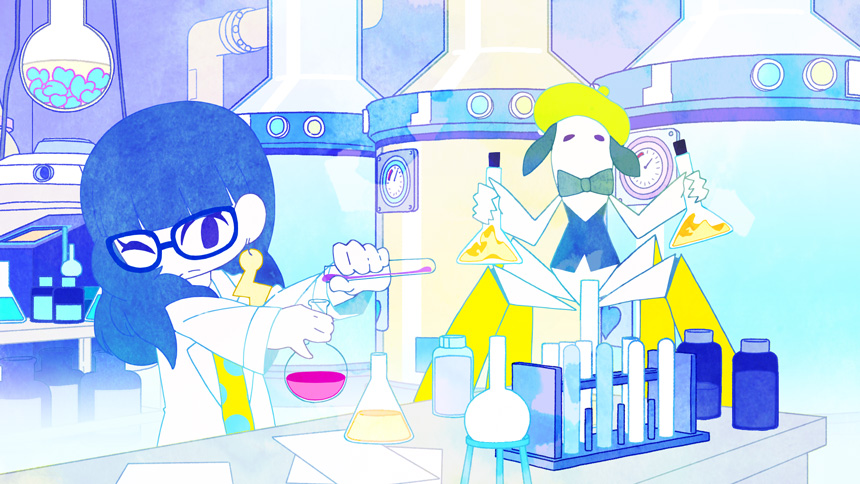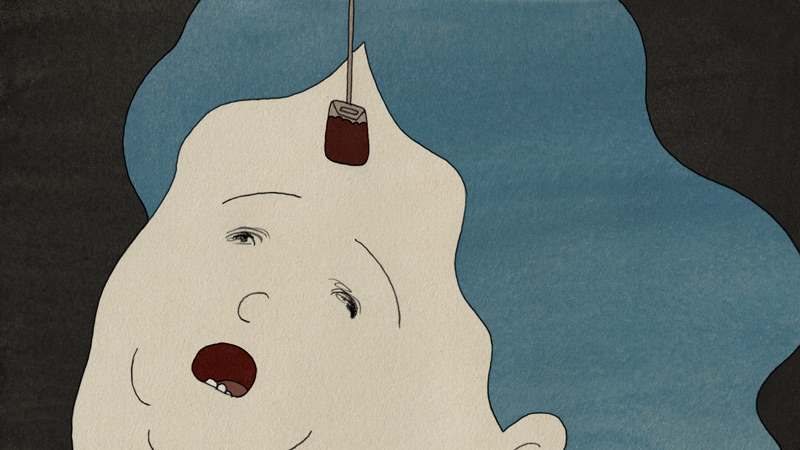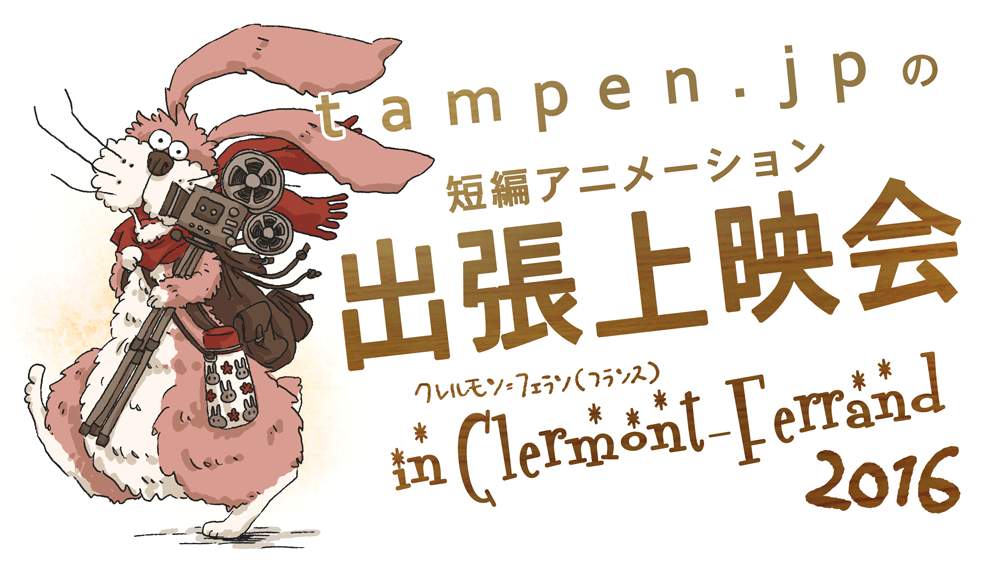新千歳空港国際アニメーション映画祭2018メインヴィジュアル:久野遥子
インタヴュー前半はこちら
土居 あと新千歳では、インターナショナルコンペティション ファミリーやミュージックアニメーションコンペティションというかたちで、ターゲットや目的に応じてカテゴリーをわけているのですが、こちらで用意した枠組みと作家のクリエイティヴの相乗効果を期待しています。
ーー今年のファミリー部門に関しては、Peter Millard監督と冠木佐和子監督の新作を選出されていて正直とても驚きました。
土居 子どもむけのアニメーションというときに、変な固定観念でもって捉えられがちな現状にたいして、僕はすごく違和感があるんですね。日本ではたとえば、抽象アニメーションは子どもにはわからないと考えられてしまったりするんです。しかし国によっては、(抽象アニメーションは)シンプルに色と音楽が楽しいということで、子どもでも楽しめるアニメーションの典型として捉えられたりもしているんですね。僕は、子どもたちには破天荒なアニメーションにも触れてほしいと願っているんです。
ーーたしかに、子どもむけのアニメーションというと、キャラクターを用いて教訓を語るような作品がまっさきに思い浮かびます。
土居 もちろん、それはそれで大切なんだけれども、そうではない作品もちゃんとみせたいということですね。そこで、ある種の「幼児性」が宿った作品ということで、Peter Millardと冠木佐和子は絶対にファミリー部門で上映したいと考えました。
Peter Millard『yes. can i play.』
冠木佐和子『ゴキブリ体操』
ーーミュージックアニメーションコンペティションもとても興味深いです。同部門は過去には、『夜明け前のレゾナンス』(百舌谷、2016年)や『Belong』(前田結歌、2016年)のようなドメスティックな作品がノミネートされていたりと、インターナショナルコンペティションとは異なる選考基準が前面に押しだされている印象があります。
土居 なぜミュージックアニメーションコンペティションをやっているのかというと、個人作家の活躍の場として、ミュージックヴィデオが重要な位置づけにあることは疑いようがないからです。そして、ミュージックヴィデオの分野でとてもユニークなアニメーションをつくりつづけている作家たちがいる。これもまたひとつの文脈であり、ひとつの「正統性」です。その文脈にいる作家たちにも、映画祭文化と接点をもってほしいという願いから(ミュージックアニメーションコンペティションを)設けています。また、もしもインターナショナルコンペティションしかなかったとすると、ミュージックヴィデオが賞をとることはほとんどないわけですよ。それはクオリティが低いということではなくて、そもそもつくられている目的がまるで違うので。たとえば今年の作品でいえば、『Hunnybee』(Greg Sharp、2018年)なんかはとてもすぐれた作品なんだけれども、一般部門でグランプリをとるのはかなり難しい。だけど、ミュージックアニメーションコンペティションという枠組みを設けることで、『Hunnybee』ような標準的な映画祭の価値観ではとりこぼしてしまう傑作をすくいあげることができる。これもまた、多様化するアニメーション・シーンに対応しようとする試みなんです。
Greg Sharp『Hunnybee』
ーーアニメーション・シーンの多様化に対応するという意味では、今年から新設された学生コンペティションも注目しています。
土居 やっぱり、まずはたくさんの作家に応募してほしいんです。そのために門扉を可能なかぎり開いていきたい。それに学生作品というのは、人生のなかでそんなにたくさんつくれるものではないので。一般的な映画祭だと学生コンペティションだけでもいくつか種類を設けるのですが、うちはひとつしかないので結果的に、そうとう選りすぐりのセレクションになっています。世界の学生はいまこういう作品をつくっている、というのが大づかみできるセレクションになっているので、日本の学生さんにはぜひみてほしいです。
ーー短編アニメーションの場合、自主制作を継続できなかったりして、学生作品がキャリアハイという作家もめずらしくはないですよね。じっさい1年間、自分の作品に集中できる環境というのはとても貴重だと思いますし、そういう環境だからこそつくれる濃密さというのが学生作品にはあると思うんですね。そういう学生作品ならではの魅力、みたいなところを押しだしていきたいという意図もあるのでしょうか。
土居 そうですね。ただ、ちょっとネガティヴな話になってしまうのですが、世界的にみても学生作品の勢いというのは落ちてきている印象があります。おそらく、卒業後のキャリアをイメージできないことが原因だとは思うのですが、「作家」をめざすひとは減りました。2000年代にデジタル技術が普及することで、ある種の制作バブルのような状況が起こったわけですが、それが長い目でみたキャリア形成に必ずしもつながらないということに、たぶんみんな気がついてしまったんですね。それとデジタル化の影響によって、独学でアニメーションをつくる作家が増えたのも一因だと思います。教育機関でアニメーションを専門的に学んでいない作家というのが続々と現れてくるなかで、学生作品という枠組みで強烈な個性をもった作品というのは現れづらくなっているように感じます。どうしても、就職のためのポートフォリオというような作品が増えている印象をいだいてしまいますね。そういう意味では、いま学生作品が陥っている状況を軽々と超えていくようなパッションをもった作品に関しては、積極的にインターナショナルコンペティションのほうに選んでいくようにしています。今年のインターナショナルコンペティションで唯一の学生作品である『OOFFEE』(Alexandros Vounatsos、2018年)はまさしく、そういうパッションに満ちた作品でした。おそらく日本ではまだ誰も知らないーーかくいう僕も選考までまったく知らなかった作品なのですが、学生がたったひとりでつくった約20分間の3DCG作品です。
ーー学生作品で20分というのはかなり長いですね。
土居 長いです。しかも、予算はたったの300ユーロ(日本円で約4万円)だそうです。どういうふうに積算したのかわからないですけれど(笑)。この作品は、なにかしらのハンデをもった男の子に降りかかる不幸を描いた物語で、おそらく作者のパーソナルな経験もかなり入り込んでいる。たぶん賛否両論になる作品ではあると思うのですが、先ほどお話ししたように学生作品にある種の合理主義傾向がみられるなかで、そういうのとはまったく異なる熱意と根性だけでつくられたような作品になっています。こういう作品もあるということを、ぜひ学生さんには知ってほしいですね。
ーー去年からの印象なのですが、映画祭で上映される作品にかぎっていえば、社会派な作品とそうでない作品の二極化が起こっているような印象をいだいているのですがどうでしょうか。
土居 今年に関してはむしろ、社会的でありながら個人的でもあるという作品が多いです。
ーーなるほど。私がすでに拝見している作品だと、『何処かへ。』(高橋良太、2018年)はまさに社会的でありながら個人的でもあるという作品でした。
土居 高橋くんの作品単体から、社会性を明示的なメッセージとして読みとることは難しいじゃないですか。でも、社会的な関心が作品のコアになっている。そういう作品が今年は多いかもしれないですね。作品の声に耳を傾けていると、個人の声も聞こえてくるというような。あからさまに「私の世界」を声高に叫ぶような作品は減ってきているように思います。
土居 短編アニメーションはお金にならない。それでもなお短編アニメーションをつくりつづけている作家は、ある種「畸形化」しているように思うんですね。どういうことかというと、観客とのコミュニケーションを必ずしもめざさない作品をつくっているということです。そういう作品は、「なぜこの作品はつくられたのか」という動機が、観客からはみえづらい。あるいは自覚的/無自覚的を問わず、作家自身が(動機を)みせないようにしているのかもしれない。いずれにせよ、制作の動機がわからないーー説明不可能なある種の使命感に突き動かされてつくられたような作品こそが、むしろ強烈な存在感を残していくような気がします。
ーーいまのお話はコンペティションの意義でもありますよね。作品単体だとわかりづらい隠された意味や価値を、キュレーションをとおして浮かびあがらせる。それは動画共有サイトなどで作品をみるのとはまったく異なる体験です。意図をもって並べられることで文脈がみえてくる。
土居 そのとおりです。だから新千歳のコンペは、いろいろな文脈が絡みあうように選んでいます。トラディショナルな映画祭の文脈を押さえる意味で、去年アヌシーでグランプリを獲得した『The Burden』や、今年アヌシーでグランプリを獲得した『Bloeistraat 11』のような作品を選ぶ一方で、ふつう映画祭では選ばないような作品も積極的にラインアップしています。あとは、うちの映画祭はアメリカの才能をピックアップすることを意識的に継続していて、西海岸出身のLou Mortonがデンマークで制作した『Floreana』などを選んでいます。他方ではもちろん、ロシアや東欧からも選んでいます。ロシアや東欧は広島に強い傾向があるのですが、そのなかでも広島では選ばれないけれどすばらしい作品をつくる、Svetlana Filippovaの新作『Mitya'Love』などを選んでいます。『Mitya'Love』は傑作なので注目してほしいですね。
Niki Lindroth von『BahrThe Burden』
Nienke Deutz『Bloeistraat 11』
Lou Morton『Floreana』
ーーまた広島との比較になってしまって恐縮ですが、広島は新しい文脈をみせるというよりは、映画祭の伝統的な文脈を自明のものとしたうえで、そこに素直に乗っかるようなキュレーションがなされいるように感じます。もちろん、広島は歴史ある映画祭だからだと思うのですが。反対に新千歳はむしろ、新しい文脈を提示することこそをめざしているように感じます。まさに好対照だと思います。
土居 アニメーションというのは、ちょっとでも文脈が異なると途端に理解されなくなってしまう芸術だと思うんですね。そうした垣根を壊したいとつねづね考えています。
ーー見過ごされがちだった文脈に光を当てるという意味では、土居さんは研究者としての執筆活動をとおして、3DCGを含めた立体アニメーションの新しい動向に注目されていますよね。じっさい近年は、立体アニメーションが存在感を増している印象があります。
土居 去年の新千歳の受賞作品も3DCGと人形アニメーションが多かったでんですよね。いま立体(人形)アニメーションに新しい美学が導入されつつあると考えています。そのなかで大きく影響したのが、Wes Andersonの人形アニメーションです。今年、日本でも『犬ヶ島』が一般公開されましたね。今回選んだ作家のなかでWes Andersonの影響が色濃く現れているのはAnna Mantzarisです。ちなみに彼女は、『犬ヶ島』にメインスタッフとして参加しています。また、短編部門の審査員を務めていただくEmma De Swaefが在籍しているスタジオは、過去にWes Andersonの人形アニメーションに人形造形としてかかわっています。Wes Andersonの人形アニメーションがあきらかに、人形アニメーションの新しい才能が集まる場として機能している事実は見逃せないです。ちなみにEmma De Swaefの新作も、長編コンペティションにラインアップしているので、そちらも注目してほしいですね。
土居 それと3DCGに関しては、かつてはある種の「3DCG恐怖症」みたいなものが(短編アニメーション・シーンには)あったと思うのですが、近年は3DCGをナチュラルに扱う作品が増えているのは間違いないです。いまのアニメーション・シーンをひと言であらわすと、「なんでもあり」だと思うんですね。なのでうちの映画祭もそれをふまえて、柔軟な姿勢は変えずにいたいと思っています。
ーーまとめさせていただくと、新千歳の短編コンペティションのカラーとは、「なんでもあり」な現在のアニメーション・シーンをまるっとみせつつも、個別の作品を越えた文脈がつかみやすいように交通整理もおこなっている、ということでよいでしょうか。
土居 そうですね。そういう意味では世界の動向に逆らわずに選んでいるつもりです。映画祭をやっていてすごく思うのは、生みだされていない作品は選べないということです。あたりまえですが(笑)。他方でセレクションのしかたによっては、ある種の偏りが生じてしまう。それは避けられない部分もあるのですが、そのせいで観客に「短編アニメーションってこういうものだよね」という固定観念をもたれてしまうことは絶対に避けたい。そのためにはセレクションする側もつねに、自分のなかの価値基準を刷新していかなければならないと考えています。
ーー大きな映画祭の場合「広島はこう」「アヌシーはこう」というように、映画祭ごとの価値基準がカラーになっていると思うんです。それが映画祭のブランドを形づくっているでしょうし。他方で新千歳は、固有の価値基準をもたないことこそがカラーといえそうですね。
土居 「特定のカラーをもたないというカラー」と考えていただければよいと思います。
新千歳空港国際アニメーション映画2018
日程: 2018年11月2日(金)〜5日(月)
会場: 新千歳空港ターミナルビル
公式サイト: http://airport-anifes.jp/