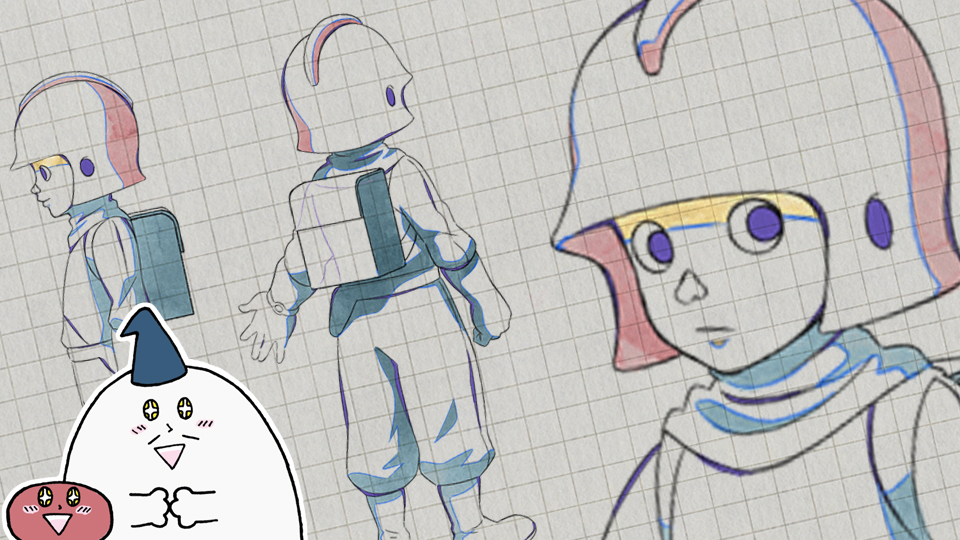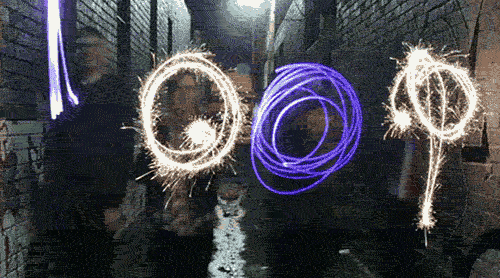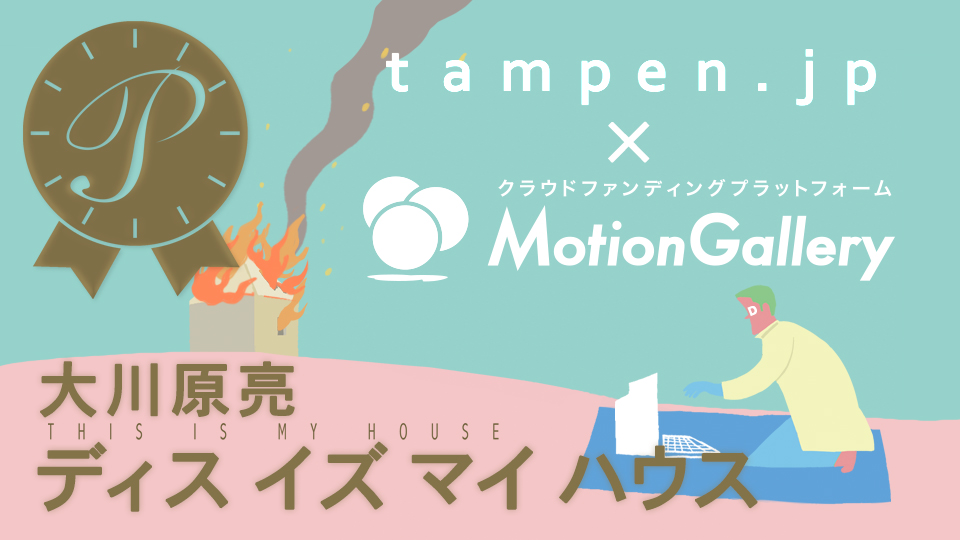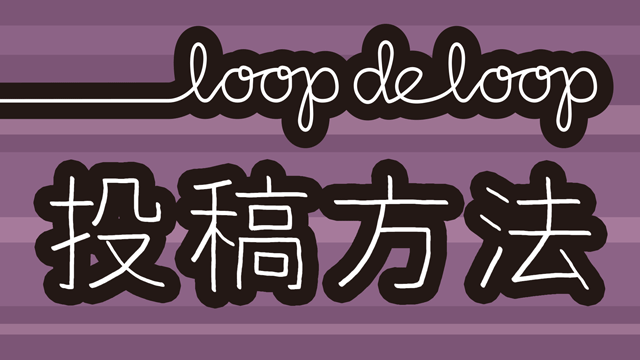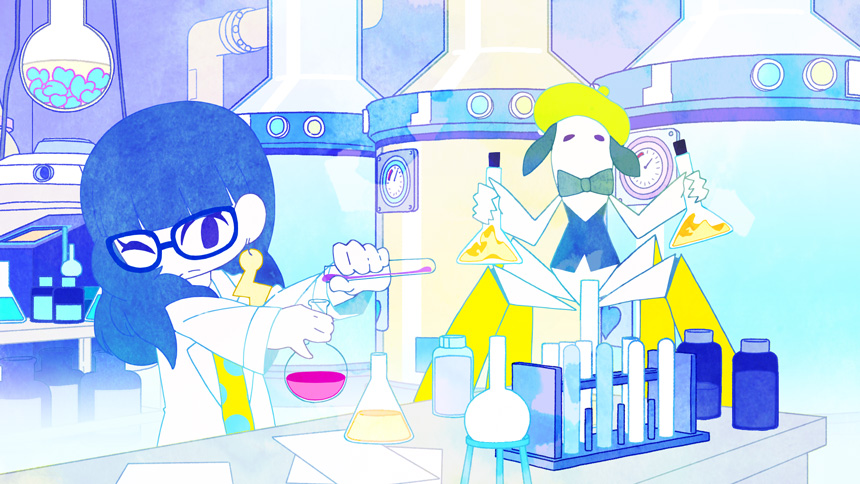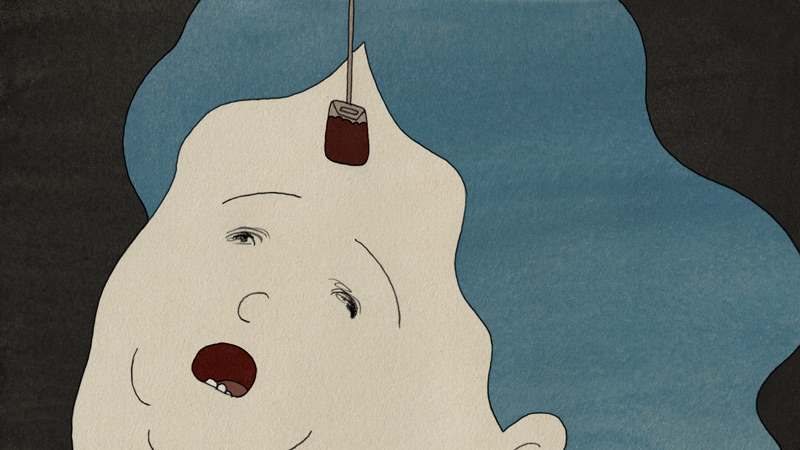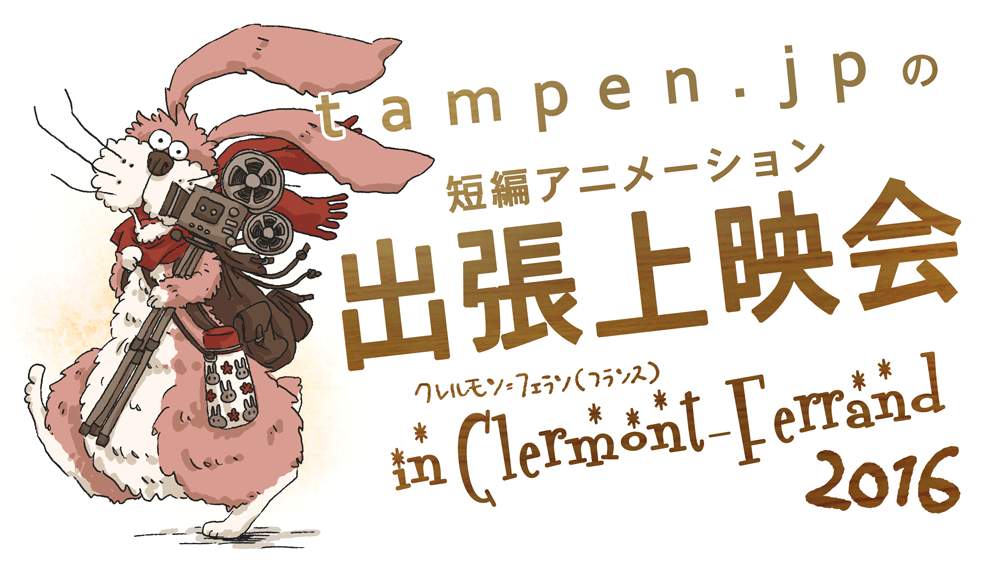アニメーションは、いまやテレビや劇場で公開される商業のアニメや、作家性と芸術性を追求する短編のアニメの上映のみならず、イベントとしての展示、現代美術での活用は珍しくなくなった。
昨年2019年を振り返れば、商業アニメーションの企画展が数多く行われたのがわかる。ざっと思いつく企画展を挙げてみても、スタジオジブリの高畑勲展をはじめ「PIXARのひみつ展」、「トムとジェリー展」など、著名な作家やスタジオを取り上げた展示が多い。
一方、現代美術の表現媒体にアニメーションを選択したケースも目出つ。たとえば日本では杉本憲相や相磯桃花、藍嘉比沙耶といった作家は商業アニメーションのキャラクターデザインを活用した作品を制作しているし、中国アートシーンでは美術作品とアニメーションを越境する作家が少なくない。
アニメーションが現代美術に生かされ、商業アニメが企画展を当たり前のように行ういま、どのような課題があるのだろうか?
そんな課題について言及したイベント「短編アニメーションの〈いま〉を知る——特集:アニメーションと現代美術」が、ディジティ・ミニミにて2020年1月18日開催。アニメーションと現代美術の状況をテーマに、現代美術キュレーターのじょいとも氏と、アニメーション/美術家の岩崎宏俊氏による講演が行われた。
なぜ商業アニメは映像をそのまま展示にできないのか? 様々な論点
じょいとも氏
まず本稿では 様々な区分の“アニメーション”が出てくるため、混乱しないようにその前提をまとめておこう。
大規模な人数で制作され、テレビや映画館で公開される、総計して30分~数十時間に及ぶ規模のアニメーションを「商業アニメーション」、個人作家が数分から十数分ほどの規模で制作する、様々な手法によるアニメーションを「短編アニメーション」と定義する。そして現代美術がアニメーションを扱うことは、「美術作品としてアニメーションを題材とする・手法を使う」ことで成立させており、映像作品とは別の見られ方がある。
さて冒頭にて “商業アニメーションの企画展が珍しくない ”と述べたが、いずれの展示もある問題を抱えている。シンプルに “商業アニメーション本編を流せない ”ことだ。商業アニメーションが美術展示の一種となったとき、鑑賞者は何を観ており、そもそもの商業アニメーションの何を見ていたのかのギャップを観て取れるのだ。
じょいとも氏は、実質的に商業アニメーションの企画展は原画の展示といった資料展示に留まっていると指摘する。対照に、美術作家によるアニメーションを生かした作品は映像をそのまま展示できていることを挙げた。
なぜ商業アニメーションは映像をそのまま展示できず、現代美術では映像を展示できるのだろうか? ふたつの違いはなにか? じょいとも氏は商業アニメーションと、アニメーションに関係した現代美術の作品を対比させながら、この問題を整理していく。その過程に商業と美術、時間芸術と空間芸術といった対照的な論点が多く含まれていた。
「そもそも、アニメーション史自体が語りづらいんです」とじょいとも氏は語る。たとえばアニメーションの原点の歴史を語るとき、フェナキストスコープから語るものだったり、日本に絞れば『鳥獣戯画』が出てきたりするのが一般的だ。しかしそれらを『この素晴らしい世界に祝福を!』深夜に放映されているようなあたりの商業アニメと比較して、関係あるとは考えにくい。
あくまでそれらはアニメーションの技術史なので、齟齬がある。ではどう見ればいいか? 他の表現をリファレンスすることだ。いまの商業アニメーションは、むしろ演劇などと比較したほうが近く、表現史の視点を含めたほうがいい。なのでアニメーション史を語るとき、技術史と表現史のふたつを見ていくべきだという。
そこでじょいとも氏は5つの論点を提示する。「時間と造形」、「動き」、「消費構造」、「フレーム」、そして「新しい自然」である。これらの論点を元に商業アニメが美術展示される要素を整理し、同時に現代美術ではそれらの論点をどのように生かしてきたかも比較していく。
時間と造形――時間芸術と空間芸術としての違い
まず「時間と造形」では、そもそも映像が時間芸術であり、美術での展示が(概ね)空間芸術という違いを説明する。たとえば商業アニメの企画展でアニメ本編の映像を展示したとする。だが鑑賞するのに快適なイスや、観やすいスクリーンやモニターを用意し、映画館みたいにしてしまえば「上映」になってしまう。それは美術展示として見るべき文脈と違ってしまうことを意味するだろう。
時間芸術と空間芸術の違いを説明するのに、じょいとも氏はレッシングの『ラオコオン―絵画と文学との限界について』を引用する。彫刻として作られたアエネイスと、詩で書かれたアエネイスのふたつを比較し、同じモチーフの作品でも、それぞれの限界を指摘する論旨だ。
こうした古典を踏まえ、ではアニメーションの持つ性質はなにか? について、時間芸術と造形芸術の中間を持つのだとじょいとも氏は説明する。
この論点を生かした現代美術の例として、やんこま氏の作品を紹介。彼の作品では複数の時間が流れている点を指摘する。たとえば絵の中のテレビによるアニメの時間、絵の中でのアニメの時間、さらに広げれば絵の鑑賞者それぞれが別々の時間を動いているという。
また先行例としてアンディ・ウォーホルの『エンパイア』を挙げた。8時間ずっとエンパイア・ステートビルを撮影しただけの映像作品であり、劇場公開もされたというが、一本の映像として観通すことを意味した作品ではない。
『エンパイア』は映像でありながら、空間芸術として展示する方法で撮られた作品ともいえる。映像を美術として解釈した古典だが、じょいとも氏は「映像展示のとき、ひとつのキーとなる」と、いまでも有効だと語った。
「動き」ではそもそものアニメーションの芸術価値として、根本的に絵が動くことそのものを取り上げる。
「動き」そのものは、現代美術においてはどのように取り入れられてきたか? じょいとも氏は動きに注目した作品を紹介していく。モホイ=ナジによる機械の動きを組み合わせ、様々な影を生み出す作品や、アニメーションの技術史的な起源であるフェナキストスコープの機能を生かした岩井敏夫の作品などを挙げた。
とはいえ、「現代のアニメーションにおいて動きはやりつくされている」ともまとめられており、これ自体をテーマとするのもまた別のアプローチが必要なようだ。この論点について、じょいとも氏は若干控えめな取り上げ方をしていたが、続く岩崎氏の講演にてこの点が掘り下げられていたと思う。
商業アニメの消費構造と “フレーム ”
ここまでの論点から一転して、人文で商業アニメーションを批評されてきた論点となる。こちらは商業アニメーションがどのように消費されてきたかを、大塚英志と東浩紀の著作をリファレンスして整理しなおしている。
大塚はビックリマンのシールや騎士ガンダムのカードダスに描かれたキャラクターや背景となるストーリーを例に、映像作品とは独立したものとして物語やキャラクターを消費していることを指摘する。その後、東はキャラの属性や要素の集積をデータベース型の消費と名付けた。たとえばアホ毛や青髪、メガネっ子みたいな記号を持つキャラを消費することを指している。
大塚・東によるサブカルチャー批評は後に大きな影響を与え、商業アニメーションの消費構造にある論点を提示したことは確かだ。これが現代美術に関係した例として、カオス*ラウンジの梅木和木の絵画作品や、瓦礫にアニメキャラの要素を描く杉本憲相の作品が挙げられた。
現代美術が商業のキャラクターアニメの消費構造を扱うことを、じょいとも氏は記号接地問題に絡めて評価する。これは「人工知能が、コンピューターの内部で扱う記号と実世界の事物ををどうやって関連付けるか?」という、記号と認識をどうつなげるかの問題を指しており、たとえば梅木和木氏の作品にそれを感じさせるという。
さて商業アニメーションでの企画展が、なぜ本編を模したジオラマ展示が多いのか? というのが当初の疑問であり、消費構造の論点を引き継ぐ形で大胆な考察が行われる。
2015年の「ジブリの大博覧会」には『風の谷のナウシカ』の王蟲のジオラマが設置されるほか、「PIXARのひみつ展」などが元の作品世界を空間として見せる試みが目立つ理由を、じょいとも氏は「フレーム」という論点から考察する。
ここでのフレームという言葉は、映像と鑑賞者の関係を表す言葉として定義される。ある映像表現において、鑑賞者はどの立場と視点に置かれているか? ということだ。
たとえばリュミエール兄弟によって映画が発明された当時の映像とは、鑑賞者にとってその現場に立ち会うフレームとして撮られている。その後、エイゼンシュタインによってクローズアップをはじめとする映画技法が生まれてから、登場人物の心理に沿ったカメラワークが発達した。
実写映画においてはカメラワークの違いによって、鑑賞者がどのフレームに置かれるかを決定しているという。
では商業アニメーションにおいて、フレームはどう機能してきたか? アニメーションを表現史として見た場合、特に商業アニメにおいては実写映画からの影響が大きい。じょいとも氏も実写映画を前提にしたフレームの論点から、カオス*ラウンジの黒瀬陽平による批評「キャタクターが、見ている」を援用する。
黒瀬氏は、『ぱにぽにだっしゅ!』などの商業アニメを例に、デフォルメされたキャラが空中に現れるような非自然的な描写を、鑑賞者は自然に受け入れていることを指摘する。これが先述の実写映画を見るフレームとは異なっているという。
黒瀬氏の批評では、「キャラクターそれ自体がフレームである」と指摘。つまり視聴者は商業アニメを観るとき、キャラクターそのものに視座を置いた前提なのだとじょいとも氏は語る。
なので商業アニメの企画展がなぜジオラマ化するのかという理由に、鑑賞者が展示を見るフレームがキャラクターそのものではないかという。すなわち常に自分自身の視点がキャラクターにあるのではないか、と考察した。
じょいとも氏は企画展やジオラマを鑑賞する体験として、似通った例にジオラマとして再現された動物園やテーマパークの例を挙げる。いずれのフレームも、「鑑賞者が自分自身のフレームによって、ある世界観に入り込んでいる」と説明する意図だ。
そこで商業アニメーションの企画展に戻ると、美術展示のような手法では、鑑賞者はキャラクターのフレームを受け入れきれないため、ジオラマ化によって空間全体である世界観を表現することで、商業アニメ本編を観る体験とのギャップを埋めているのではないか、と語られた。
ではキャラクターそのものがフレームとなることを、現代美術にした場合どうなるのか? その例として相磯桃花のインスタレーション作品が挙げられた。「人間じゃない!」展では、プロジェクションやVRを見るHMDを利用し、あるBLや乙女ゲームに出てくるような男性キャラクターがオナニーを繰り返すという、グロテスクな作品が展示された。
ここでは鑑賞者が「キャラクターをフレームにおいた」状態であれば、いずれの仕掛けも座りの悪さがあり、いわばフレームを揺さぶられる体験となっている。商業アニメのキャラクター表現を美術展示として見せるときの、ある種の批判性を発揮しているといえるだろう。
じょいとも氏は最後に「新しい自然」という論点を提示。ここまでの論点と異なり、「地球が人工物で満たされ、虚構と現実が曖昧になったり、あるいは両者が侵食しあう」という、現代的な自然についてだ。
佐藤雅春の作品。現実のなかにアニメーションが入り込む違和感を描く
「新しい自然」の例として、ナム・ジュン・パイクのテレビが森の中に配置された作品や、佐藤雅春による、実写映像のなかにロトスコープによるアニメーションが入りこんだ作品のように、自然のなかにテクノロジーやサブカルチャーが入りこんだケースを挙げた。
これは現在インターネットやスマートフォンによって社会インフラが変わり、それらを通して現実を見ることが当たり前になっている。ここにVRやXRなどが加わり、さらに2次的に現実を観る環境は進みつつあるだろう。それではなく、アニメや映画などのサブカルチャーが現実のなかで自然に浸透している状況を鑑みれば、じょいとも氏が提示した「新しい自然」という論点は興味深いものがある。
まとめとして、じょいとも氏は「アニメーションは実写よりも、映像の持つ問題を露わにするメディアだと思う」と語った。その問題が見える場所として、アニメーションの展示に注力していくという。商業アニメが美術展示となったり、あるいは現代美術として生かされた場合どのようなものが観られるかがまとめられたセッションといえるだろう。
短編アニメーションと現代美術の価値
岩崎宏俊氏
さて実際の作家側にとって、アニメーションと現代美術はどのように関わっているのだろうか? 続くセッションでは岩崎宏俊氏が担当。ここでは「商業アニメーション」の視点は一旦置いておいて、主に「短編アニメーション」と「現代美術としてのアニメーション」の境界を行き来することについて語られた。学生時代の2000年から、作家活動を行う2020年現在までの自身の経歴や体験を語った。
岩崎氏の経歴は「アニメーション作家/美術家」となっているように、短編アニメーション作家でありながら同時に現代美術の作家でもあるという、境界線を踏んだものとなっている。このキャリアを自覚的に歩んでいるそうで、セッションでは実体験を踏まえて短編アニメーションと現代美術の表現の違い、そして作家活動として収入を得る違いについても言及した。
岩崎氏は主にロトスコープを使ったアニメーション制作を行っている。これは実写映像を下敷きにして、その上からアニメーションにしていく手法である。古くはアメリカのフライシャー兄弟が発明し、アニメーションに生かしたほか、ディズニーなどの商業アニメーションから短編アニメーション、そして先述の佐藤雅春の美術作品に利用されているのだ。
岩崎氏はもともとアニメーションを目指していたわけではなかったそうだ。美術大学の学生時代は実験映像を志向していたそうで、様々な作家や展示を観たり、手法を模索していく中でロトスコープに出会ったという。
代表作『DARK MIXER』は、まさしく現代美術と短編アニメーションの境界を踏み越えるプロジェクトとなった。もともとは現代美術のインスタレーションであり、50個のループするアニメーションを並べて配置し、「運動のデペイズマン(※)」を提示する作品だった。これをシングルチャンネルの映像作品として20個の映像をまとめたものに仕上げ、様々な映画祭に応募していったのが上記のアニメーションである。
(※「デペイズマン」本来あるべき環境から別のところへ移すことによって異和を生じさせるシュルレアリスムの中心的な概念のひとつ。仏語で「国外へ追放する」「異郷の地へ送る」などの意味を持つ)
岩崎氏はどのようにして、アニメーションを美術として認識するようになったのだろうか? きっかけとなったのは、まだ実験映像を志向していた2002年に見た企画展「スクリーン・メモリーズ」だった。これは “20世紀のコンテンツである映画を、いまこそ美術として捉え直す”ことをテーマとしており、作家と鑑賞者の関係そのものを捉え直す意図があった。そこで特に注目した作家がウィリアム・ケントリッジだったという。彼の作品はドローイングを1コマずつ撮影してアニメーションにするという、美術とアニメーションの境界を超えた作り方をしていたからだ。
そうした経緯の後、2005年の卒業制作にて、初めてアニメーションを作り始めたという。そのときに個人の短編アニメーション作家や美術としてアニメーションを用いる作家がいることも知っていったそうだ。
またこの時期には短編アニメーションを取り巻く環境が活況になりつつあった。NHKのデジスタが全盛期を迎えた時期であり、文化庁メディア芸術祭がアニメーションを評価対象にする動きが観られたのだ。
やがて2010年代に近づくにつれて、短編アニメーションと現代美術の境界を踏み越える作家が増えてきたという。キュレーターや作家によって作品の意味が変化していく時期だった。岩崎氏は「いろいろと考えさせられるきっかけが多かった時期でした」と振り返り、2010年までアニメーションと美術について話せる人がいなかった、と難しい環境だったことを語った。
現代美術と短編アニメーションを越境する時代
2010年代に入ると、現代美術と短編アニメーションを越境するケースがさらに見当たるようになる。とりわけ中国の作家たちにそうしたケースが数多く見当たるという。主に70年代から80年代生まれの作家は境界線を踏み越えて柔軟に活動している。主にスン・シュン、ゲン・シュエ、そしてレイ・レイらが活躍しているそうだ。
岩崎氏はアニメーションがいかに現代美術となるか? の具体的なプロセスも説明。彼らは美術館やギャラリーに入るか、美術商に作品を買い取られることでアートマーケットに入り、作品は美術としてのお墨付きを得るという。「重要になるのは、いかにアニメーションであることを(現代美術として)プロモートするか」だという。
アニメーションをアートマーケットに売り込むには?
岩崎氏はあらためて、映像作品と現代美術におけるマーケットの違いについても語った。まず映像作品には配給会社がつき、パッケージの売り上げから収入を得るビジネスモデルである。たとえば個人のアニメーション作家の場合、作品のパッケージや配給、映画祭の賞金が主な収入となる。
作品を現代美術として販売する場合、事情は大きく異なる。版画のように作品の複製が可能な表現媒体と同じく、版画のように “エディション ”という形で販売するのであるという。たとえば制作したアニメーションのDVDを販売するならば、生産する数を絞り、1枚数万円〜数十万円で販売することで、価値を上げたものにするのだ。ギャラリーで販売する場合は、ギャラリーと作家側の取り分は基本的に50:50になっているという。
また購入したアニメーションを、絵画のように壁に掛けて展示したい場合、映像作品が入ったモニターごと販売したり、データそのものを売るかたちなどがある。これらはアートマーケットがメディアの発達と共に変化した結果だという。最新のビジネスモデルが知りたい人は、作家の個展やアートフェアを観ることで作品の売り方が見えてくるそうだ。
またアニメーションの場合は映像作品の原画を販売する方法もあるが、これがひとつの作品である美術作品のように高額にはなりにくいのは、アニメーションのメインはあくまで映像であり原画ではないこと、また原画サイズが小さいことが考えられるそうだ。例外はウィリアム・ケントリッジの作品だ。ケントリッジは一枚の紙に描いては消すプロセスで制作されるため、原画はその1枚しかなく、なおかつ原画のサイズも通常の作画用紙に比べて格段に大きいため、そのため価値が大きくなっていると考えられるそうだ。
岩崎氏はまとめとして、アニメーションを美術とする場合には、どのようにプロモートするか文脈の見直しも必要になると語った。とりわけ現代美術は制作の技術は当然ながら、その先の文脈をどのように考え直すかによって、作品となるかどうかが別れる分野だ。「(アニメーションを)実験映像などの文脈と見直していけば、美術との繋がりも見えるかもしれない」と岩崎氏は展望を語る。
最後に岩崎氏はアニメーション表現の可能性について言及。そもそものアニメーションという言葉にはAnima(魂)やAnimate(生命を与える)という意味合いもよく語られるが、こにAnimalを加え「アニメーションはその動物性を追求すべきだ」と語った点が斬新だった。
「アニメーションはすでに多様になっているため、そういった方向に回帰させるときではないか」と岩崎氏は語る。アニメートとは単に絵を記号的なものにせず、むしろ書き換えていくものだと考えているそうだ。「アニメーションのメタモルフォーゼは、観ている自分たち自身が書き換えられ、変容するもの」と岩崎氏は可能性についてまとめた。これはじょいとも氏が挙げた「動き」の論点を補足する視点とも言えるだろう。
詳しいセッションの模様は、YouTubeのtampen.jpのチャンネルでも公開されている。細かな内容はこちらもチェックしてほしい。