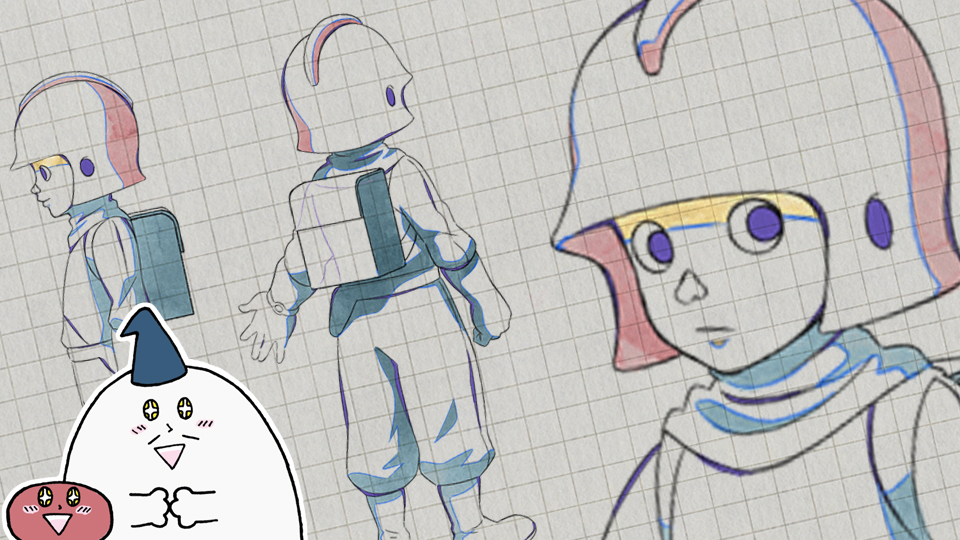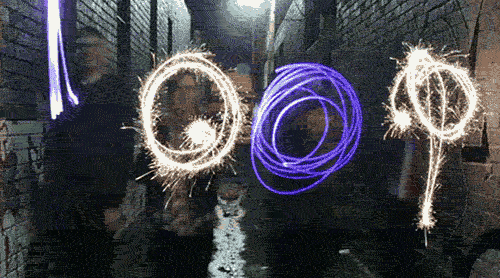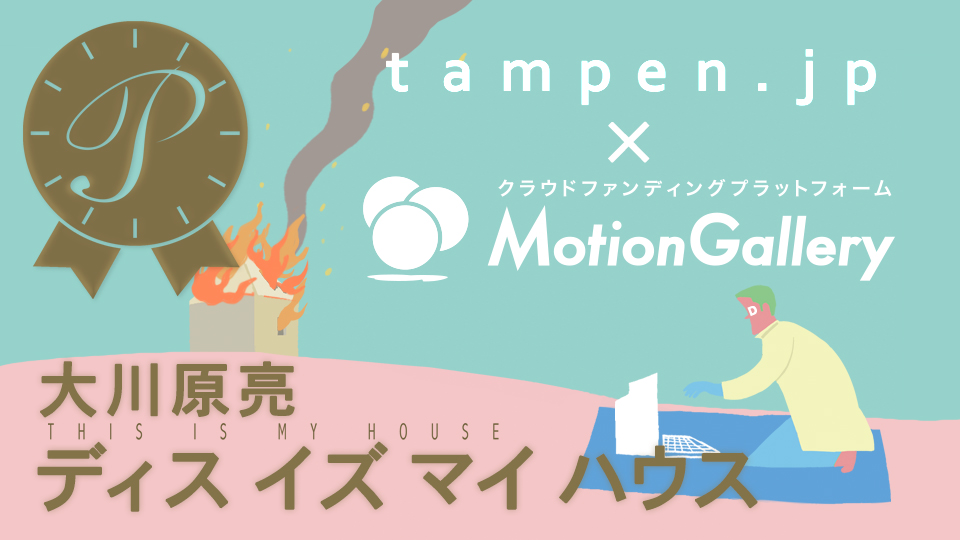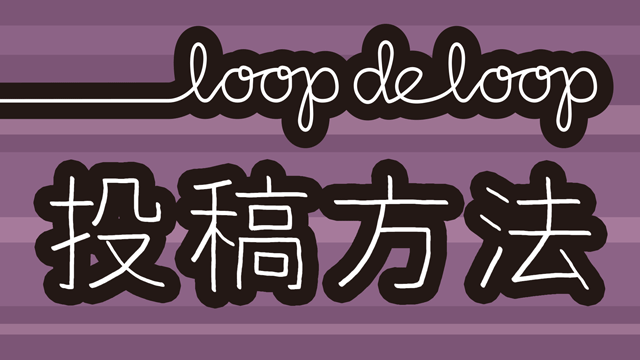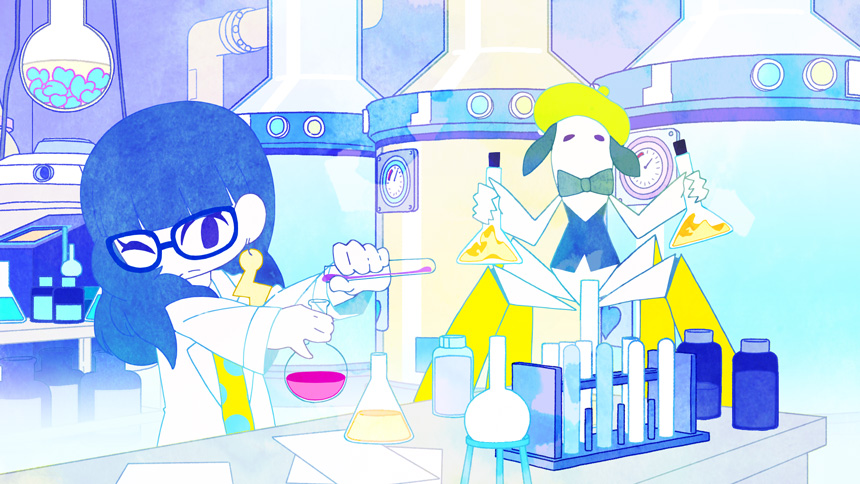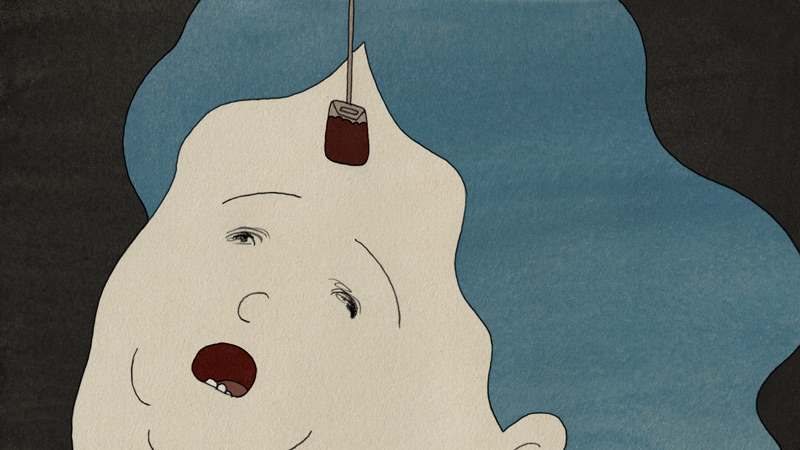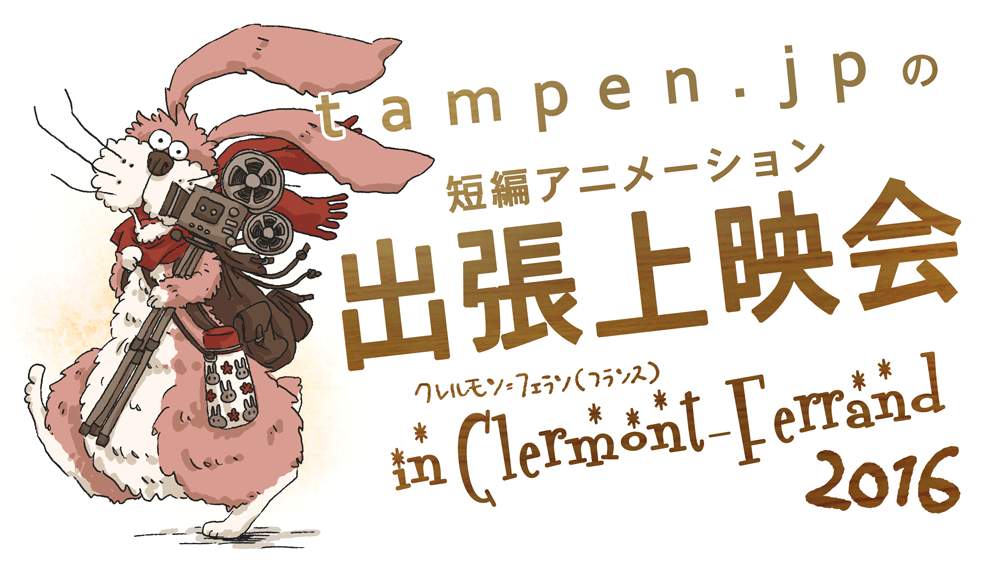tampen.jp主催上映会「短編アニメーションの〈いま〉を知る——特集:大内りえ子=孤独でも自由なもうひとつのキャラバン」が2019年7月27日と28日の二日間にわたり開催された。同上映会は、「短編アニメーションの〈いま〉を知る」シリーズの一環として企画され、アニメーションをたんに「みる」だけではなく「考え」「語る」きっかけとなる場をめざした。具体的には上映後のトークにて、監督自身のみならず、三人の批評家をゲストに招いて、大内監督について多角的に論じてもらった。さらに議論を深めるために、登壇した批評家たちには後日、大内監督に関するレヴューを執筆してもらうことになっている。その第三弾として、視覚文化評論家の塚田優によるレヴューを公開する。これをきっかけにして、個人アニメーションについて「考え」「語る」文化がわずかでも活性化することを願う。
大内りえ子論——匿名的な「肉」についての試論
塚田優
アニメーションを論じるにあたって、しばしばその解釈の糸口とされるのは「記号性」である。記号学者のユーリー・ロトマンは論文「アニメーション映画の言語について」(『映画の記号学』所収、大石雅彦訳、平凡社、1987年)のなかでアニメーションを「記号の記号」であると言い、他の芸術の約束事を引用することによって成り立つ性質を指摘している。大内りえ子は、日本のマンガや商業アニメーションの様式を引用し、作品を制作する。類型的な要素の組み合わせから構成される大内の作品は、アニメーションの記号性を積極的に引き受けたものとして理解されるべきだろう。
しかしフィルモグラフィーを通覧すればわかるように、物語表現としてのマンガやアニメの約束事に大内の作品は必ずしも順従ではない。ゆえにその独自性は絵柄そのものではなく、映像固有の時間性、つまりカットとカットをつないでゆく編集に存在している。例えば『返事をする;繰り返す 繰り返した;消す;特に好き 特に好きじゃなくなった。』(2014年、以下『返事をする』)を取り上げよう。その他の作品と共通している傾向でもあるが、本作は散文的なカットのつなぎで構成されている。繁華街やガード下、汚部屋といった現代的なモチーフを中心に様々なイメージが映し出されるのだが、はっきりとしたストーリーは読み取れない。哲学者のジル・ドゥルーズはかつて映画を知覚することについて、向かい合う人物を切り返すリヴァースショットによるカットつなぎを、無前提に「眺める者・眺められるもの」の関係として理解することへの懐疑を表明する。なぜならその切り返された映像は、最初に映された人物の主観として文法的に認識出来ると同時に、それ自体が自立したイメージとして鑑賞者に差し出されているものでもあるからだ。ゆえにドゥルーズは、映画のイメージついて次のような性格を見出している。
映画的な知覚イメージが、絶えず主観的なものから客観的なものに、また客観的なものから主観的なものに移り行くのであれば、そうした知覚イメージにはむしろ、しなやかで凝固しない独特のあり方を求めるべきではないだろうか。(ジル・ドゥルーズ『シネマ1*運動イメージ』財津理/齋藤範訳、法政大学出版局、2008年、129頁)
『返事をする』にはクリック音が複数のカットにまたがる一連のシークエンスがあるが、こうした音響的な処理もあいまって、イメージとイメージの境界は滲みだし、ドゥルーズが特徴づけたような「しなやかで凝固しない独特のあり方」へと近づいていく。こうした事態に気付くことによって、本作のイメージ群はひとつのかたまりとして私たちに語りかけてくる。セミコロンが多用されたタイトルは、ピリオド(分離)ともカンマ(結合)とも異なるカットの関係性を象徴したものに他ならない。
そうした編集メソッドを確認したうえで指摘したいのは、大内作品に頻出する生物学的な描写である。『カーテン カーテン カーテン』(2014年)では遺伝子の螺旋構造を彷彿とさせるシーンがインサートされ、『私には未来がある』(2016年)に登場する少女たちはあたかも細胞分裂をするかのように増殖する。とりわけショッキングなのは、『返事をする』において女性キャラクターの乳房が輪切りにされて落ちていくシーンだ。ここにはキャラクターの固有性に対する批判が見出せる。作家 / 批評家の大塚英志は著書『アトムの命題——手塚治虫と戦後まんがの主題』(徳間書店、2003年)において、手塚作品における登場人物の流血にリアリズムを見出し、逆説的にマンガのキャラクターに固有の実存が付与されたことを指摘する。大内は、こうした認識を覆す。本作のスプラッター映画のような切り株表現は、キャラクターの内部にあるのが単なる肉でしかないことを暴き、そのアイデンティティを剥奪するのだ。
キャラクターたちは、肉体を伴った個体として描かれているものの、その匿名性から逃れることができない。このことを作家自らの身体を用いて表現したのが『りえりえこのおまめ生活地獄編』(2019年、以下『おまめ生活』)である。ここで大内はアプリケーションで作成した自らのアバター・りえりえこと同じ画面にVRヘッドセットを被って登場する。『おまめ生活』は3DCGによるアバターと自らを対比することによって身体性を強く打ち出した作品であるが、ラストショットの性器の模写が、大内りえ子という個人の身体すらも生物へと抽象化してしまう。
これまで大内は多くの作品で裸体を描くことによってキャラクターの個性を剥奪し、匿名的な存在として扱ってきた。『おまめ生活』はこうした倫理をより直接的に提示したものである。ここにはどこまでいっても匿名的な肉体でしかない人間の姿が記録されている。本作はキャラクターへの関心を肉体そのものへと還元することでアニメーションというメディウムを括弧にくくり、表現をより一般化することに成功した作品だと言えるだろう。その匿名的な「肉」のうごめきを、今後も注視したい。