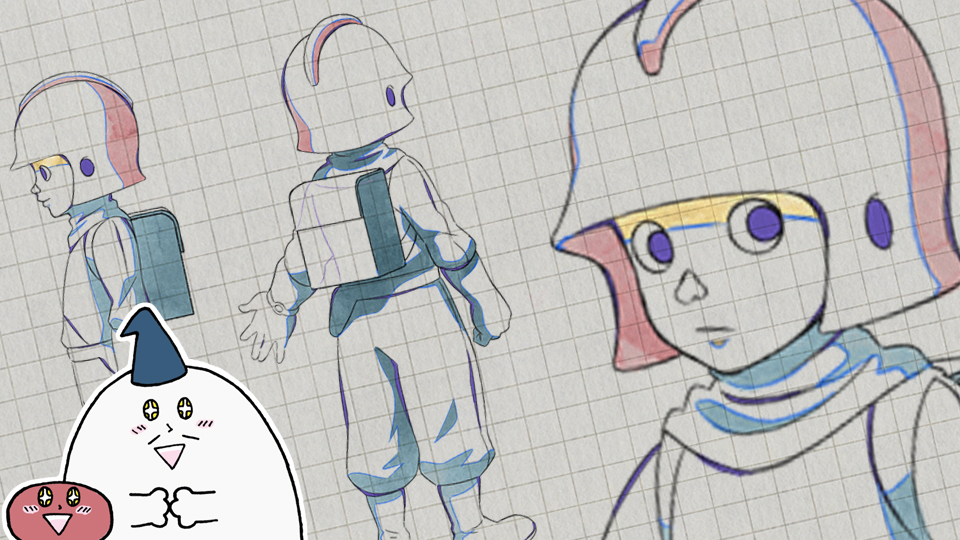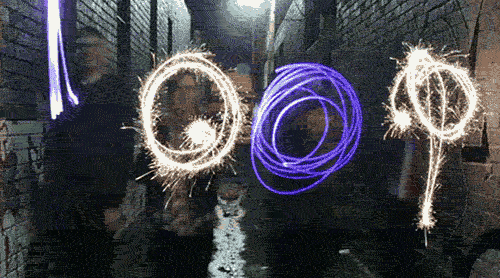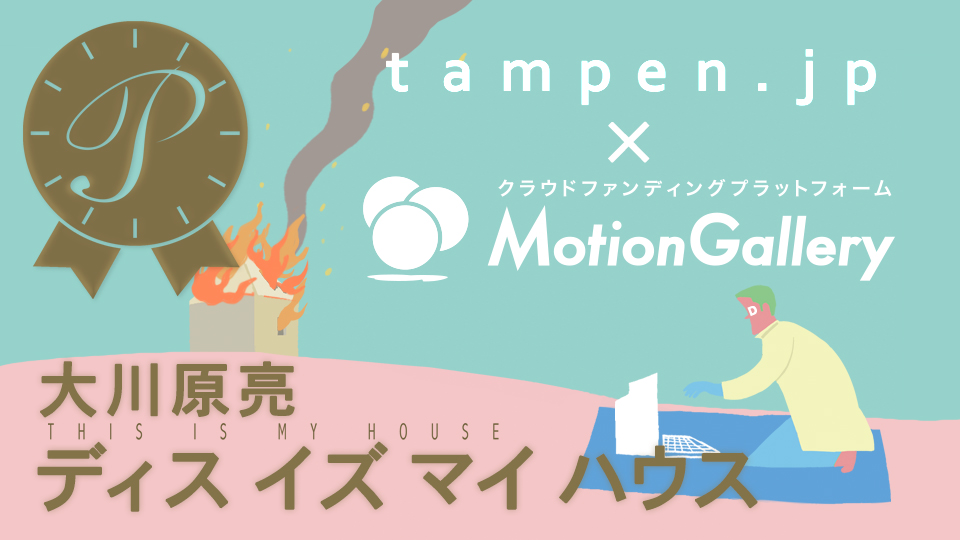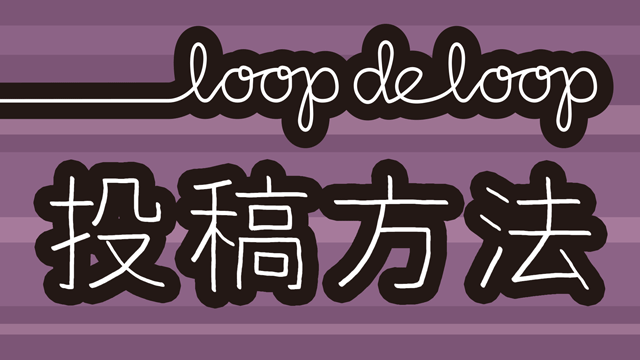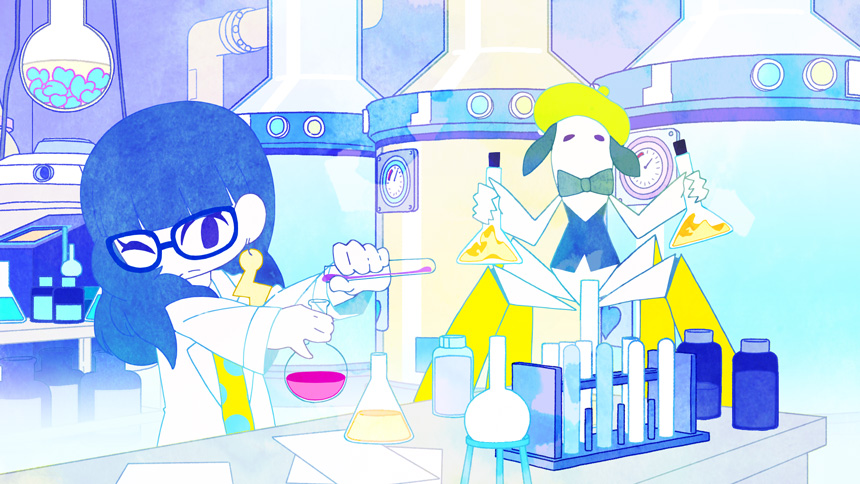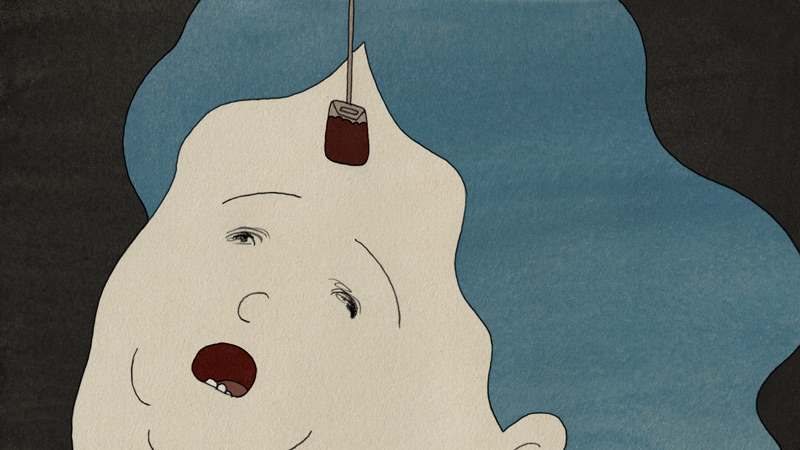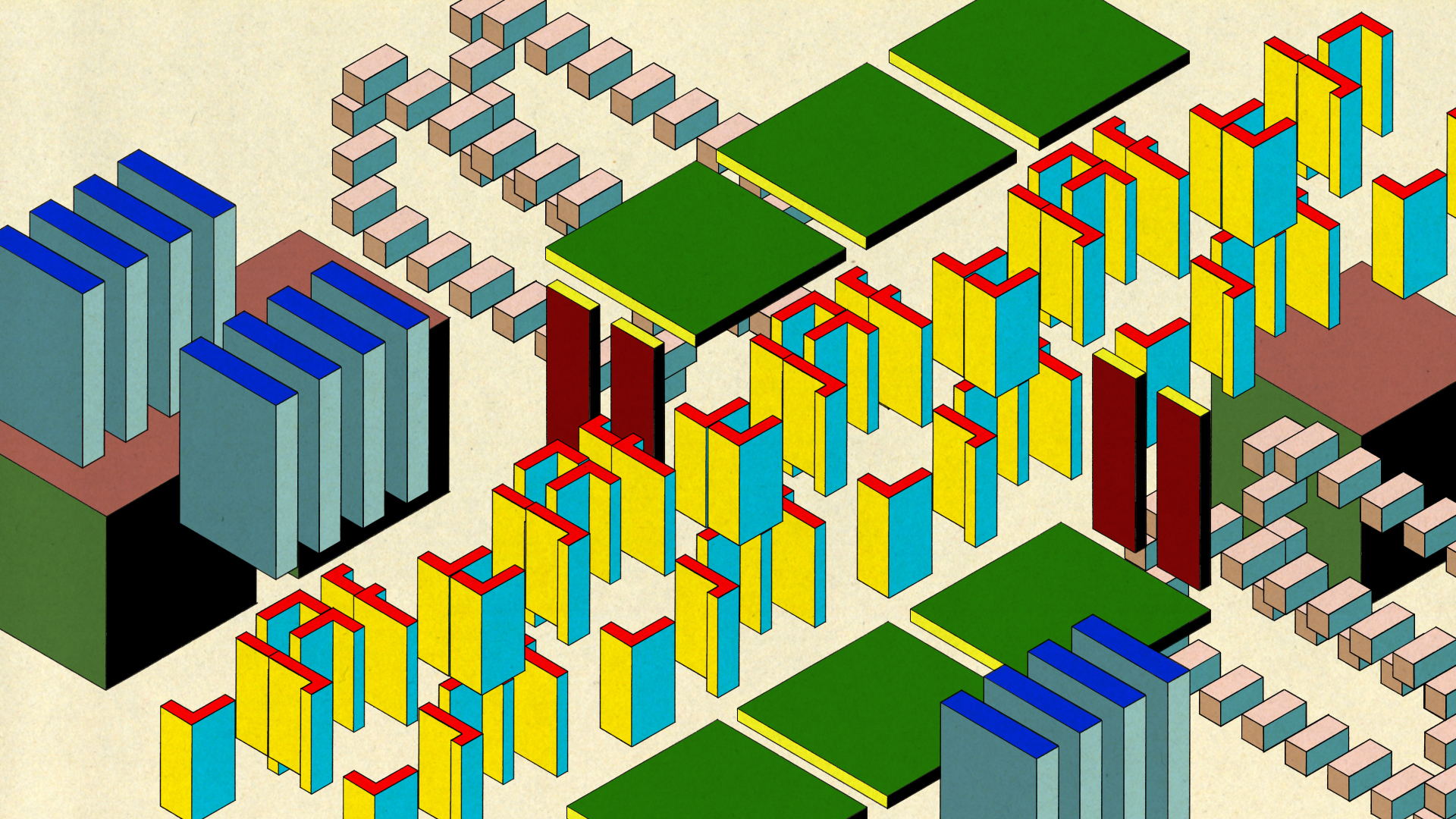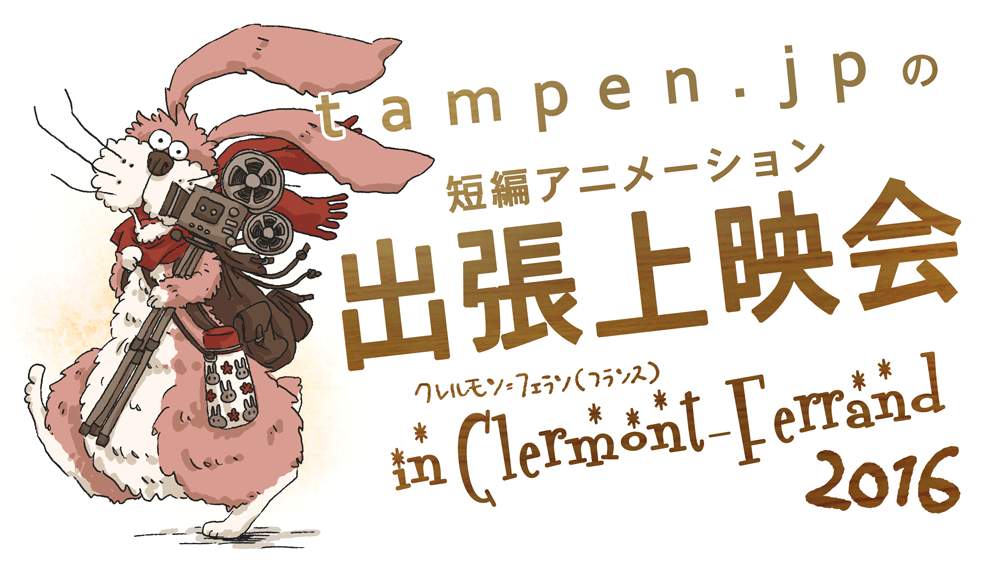Part 1では、作品完成までの道のりや、テクニカルな話題が中心だった。Part 2ではより、水江監督の創作の背景に迫っていく。Part 2で興味深かったのはやはり、水江監督のなかに芽生えた「物語る」ことへの欲求にかんする話だ。水江監督は従来、「ノンナラティヴ」な作家として語られてきた。それは水江監督自身の戦略によるところも大きい。ところが最新作『DREAMLAND』では、あきらかに「物語性」を志向している。いったい、水江監督のなかでどのような心情の変化があったのか。水江監督いわく、「物語性」の萌芽は前作『WONDER』に、すでにあったという。
ーーここからは質問の趣向を変えたいのですが、水江監督の作品は、「抽象アニメーション」とひと括りにされがちですがじっさいは、「細胞アニメーション」と形容されるような有機的なアニメーションと、『DREAMLAND』のように幾何学図形が展開する無機的なアニメーションのふたつに大別できます。このふたつの違いを、水江監督ご自身はどのように意識していますか。
水江 そのふたつの違いについては、はっきりと意識しています。まずは有機的なアニメーションですが、これは究極的には自分自身のことなんです。自分自身のことであり、全人類のことであり、全生命のことでもある。これから生まれてくる生命。すでに死んでしまった生命。そういうすべてをひっくるめて「生」を肯定したい。その一心ですよね。『WONDER』が典型的だと思うんですけれども。『WONDER』も最初は、「365秒間メタモルフォーゼしつづけたらおもしろいぞ」という思いつきみたいな発想から出発しました。制作の途中で自分の引きだしをすべて開ききってしまって、そこから先はアイディアを絞りだすようにして制作しました。最終的にはほとんど、自動筆記のような状態で。作画用紙に絵具やクレヨンでいきなり描いたりして、最後のほうは絵具を手に取ってアクション・ペインティングのようにして描いていきました。すると、「このまま自分が幼児に戻って消えていく」というイメージが、ふっと頭に浮かんだんです。とにかくハイな状態になっていましたね。(作業の)ペースもどんどん上がってくる。大気圏に突入した隕石がシュっと燃え尽きるようなイメージです。『WONDER』は、最初と最後が真っ白な画面なんですけれども、同じ白色でもよくみると違う。最初が紙の白で、最後が絵具の白なんです。循環しているようでじつは、ステージがひとつ上がっている。ちょうどうずまき模様のように。僕なりに、生命の循環というか、ユニヴァースを肯定しているんです。
他方で無機的なアニメーションはなにをイメージしているかというと、「人間によってつくりだされたもの」です。自然に生みだされたものではなく。(無機的なアニメーションのほうは)「人間がつくってきたものとはなんだったのか」というようなことに思いを馳せながら制作しています。以前、奈良ドリームランドの廃墟に行ったことがあるのですが、アトラクションなどはすでにボロボロでした。かつては休日ともなれば大勢の人が楽しく過ごしたこの場所も、いまでは訪れる人間も管理する人間もいなくなって、それでも場所だけは廃墟になっても残りつづけているというのをまのあたりにしたとき、「人間がつくったものにたいして、最後まで責任をもちつづけることはできないのではないか」という考えが頭に浮かんだんですね。遊園地は形あるものだけれど、社会のシステムや制度も同じようなものですよね。それをつくりだした当事者がいなくなったあとも、システムや制度は残りつづけて後世まで影響しつづける。そういうことを考えてしまったんですね。じっさい奈良ドリームランドは、『DREAMLAND』のモデルでもあります。
ーーおそらく、いまのお話ってとても重要だと思います。というのも水江監督はずっと、「ノンナラティヴ」な作家と考えられてきた。
水江 戦略的に自分から名乗っていたというのもありますからね。多くの人は、アニメーションといえば物語があるものと思っている。だから、「物語がない」とあえて自分から言うことで、興味をもってもらえたりもしました。
ーーただそのせいで、水江監督のポテンシャルがみえづらくなってしまっているかもしれない、とも思うんですよ。お話をうかがっていると水江監督のなかにもやはり、「物語」にたいする欲望があるように思えてならない。「物語性」の萌芽は『WONDER』にすでにあると思うのですが、『DREAMLAND』では(「物語性」が)ますます打ちだされていますよね。
水江 まさにそのとおりですね。『DREAMLAND』は「物語」をはっきりと意識して制作しました。後輩の作家とかにも、「『DREAMLAND』は物語映画だよ」とはっきり話しています。だからこそ、(『DREAMLAND』の)冒頭と末尾に文章を挿入しています。
ーー架空の挨拶文と、『創世記』から「バベルの塔」の一節を引用している部分ですね。
水江 そうです。少しでも(観客の)手がかりになればよいなと思って。ただ、(文章を挿入することを)そうとう悩みました。自分はずっと、「ことば」に頼らないアニメーションをつくってきて、(「ことば」に頼らないアニメーションを)期待されているのはわかっていたので。(観客から)批判もされるだろうなと。批判も覚悟しています。
ーーそれだけ水江監督のなかで、「物語る」ことへの欲求が高まっているということなのかもしれませんね。なにかきっかけがあったのでしょうか?
水江 きっかけはいろいろあったと思うんですけれども、でもやっぱり『WONDER』がひとつの契機だったかもしれないですね。(『WONDER』以前は)快感原則というか、観ていて気持ちがいいというのをめざして制作していました。でも『WONDER』にかんしては、(観客が)自分の人生を思いだすような作品になってほしいと願いながらつくっていました。その後、『WONDER』でベルリン国際映画祭にノミネートされたときに、いままでもらったことがないような感想をたくさんいただいたんですね。一緒にノミネートされたアメリカ人の監督からは、「これは愛についての物語だ」と言われたり。ある一般観客の女性からは、「(『WONDER』を観て)私も明日からは、普段着ないようなカラフルな洋服を着て、日常にもっとワンダーを取り入れたいと思ったわ」と言われました。みんな自分の人生に引きつけて作品を受け止めていたんです。その経験をとおしてあらためて、作品がもつ力みたいなものを実感しました。『WONDER』では、それがすごくポジティブな方向に作用したわけですが、『DREAMLAND』のほうは、いまの自分を取り巻く世界だったり状況というものを、立ち止まって考えさせるようなものにしたかった。
ーー水江監督は2015年に、ミャンマーで「抽象アニメーション」のワークショップを開催しています。そのときの経験について以前、イベントで語られていましたよね(「ANIME-ASEAN 軍事独裁政権下で映画祭をはじめるには――ミャンマーの現代映画シーンと生まれつつある個人アニメーション」2017年5月7日、シアター・イメージフォーラム)。その内容は、軍事独裁政権下で政治や社会にたいする不満を堂々と表明することがリスキーな状況のなかで、ワークショップ参加者たちが、「抽象アニメーション」にはじめて触れて、無意識のうちに抑圧していた感情をアニメーションをつくりながら解放していく様子にとても可能性をかんじた、というようなものだったと記憶しているのですが……。
水江 そういう話をしていましたね。
ーーそのお話をうかがったときに、言語化される前の、もしかすると本人すらも自覚していない情動をダイレクトに媒介する力が、「抽象アニメーション」には宿っているのかもしれないと思ったんですね。ミャンマーでの経験は、その後の制作に影響を与えましたか。
水江 やっぱりミャンマーでの経験はすごく大きかったですね。権利や自由がすごく抑圧された状況のなかで、歌や絵といった芸術が、眠っている人々を呼び起こすというのを実感しました。自分が教えていてもやっぱり、目に見えて作用していくんですね。
ミャンマーに滞在しているときに、あるアーティストの展示へ行きました。ひとの手を石膏で型抜きしたものがずらっと並べられていて、その手はすべて、政治犯として投獄された経験のあるアーティストの手から型抜かれているんです。型抜きの作業をしながら同時に、どういう理由で逮捕されたのかインタヴューをしていて、その様子を記録した映像も一緒に展示されていました。それを観てやっぱり、とてもショックを受けたんですよね。単純に大勢のアーティストが表現を理由に逮捕されているという事実を実感したのもありますし、表現をすることにすごくリスクがある状況というのを実感しました。しかも、(作者だけでなく)会場を貸したギャラリーや鑑賞者も逮捕される可能性がある。つまり、みんながリスクを背負いながら、それでもなお芸術と向き合っているんです。それってすごく勇気がいることだなと。そのときの経験というのは、『DREAMLAND』をつくっていくうえで大きく影響しましたね。
Part 3へつづく