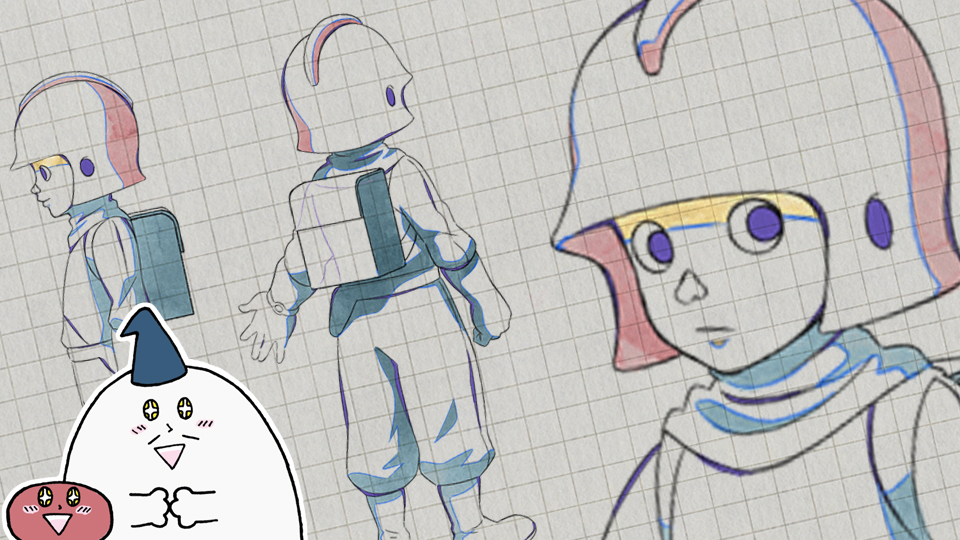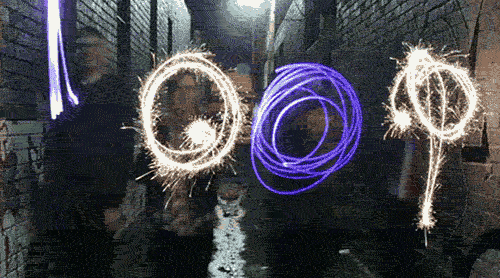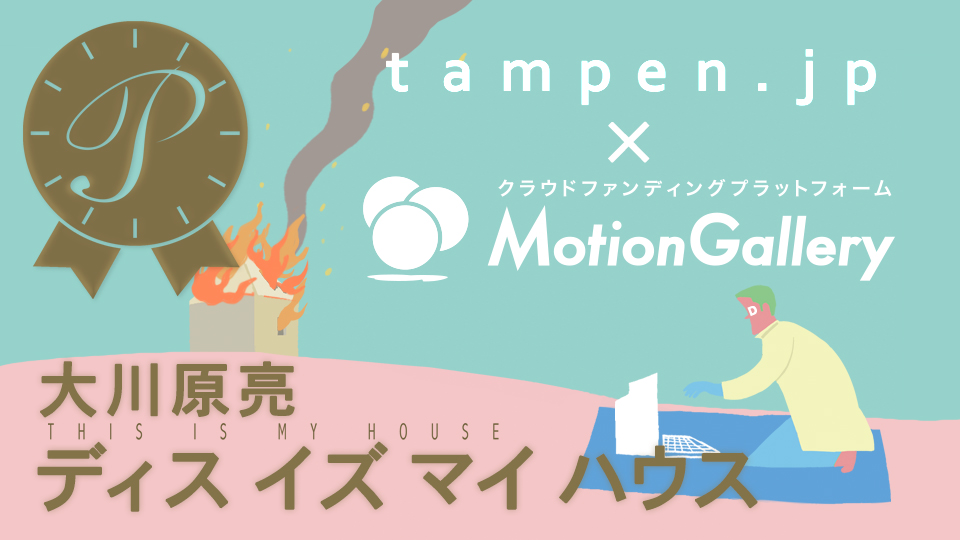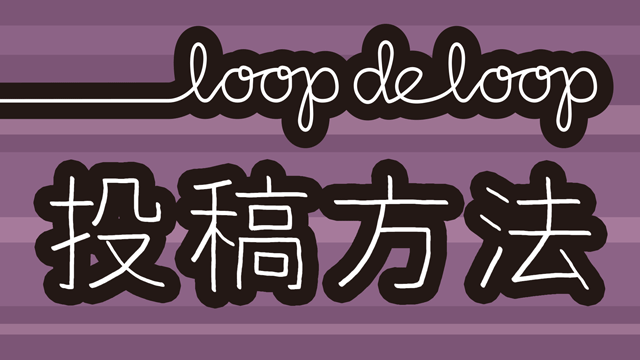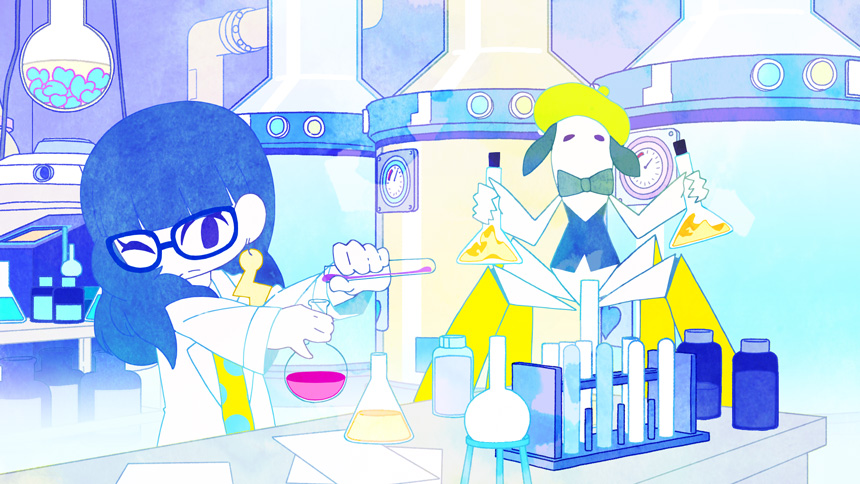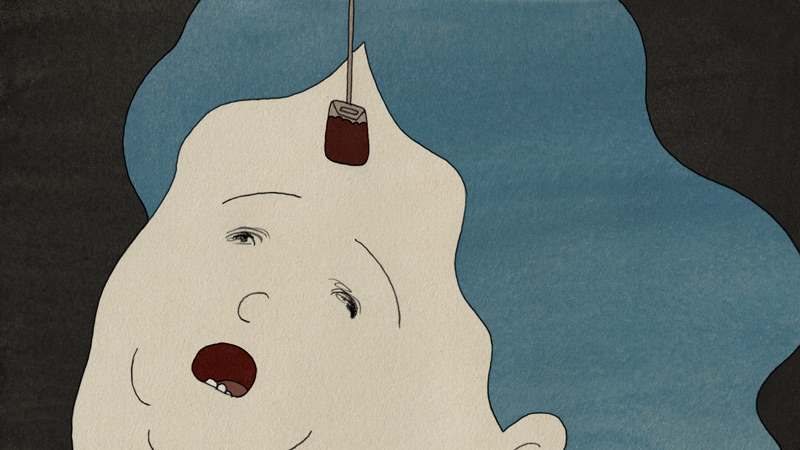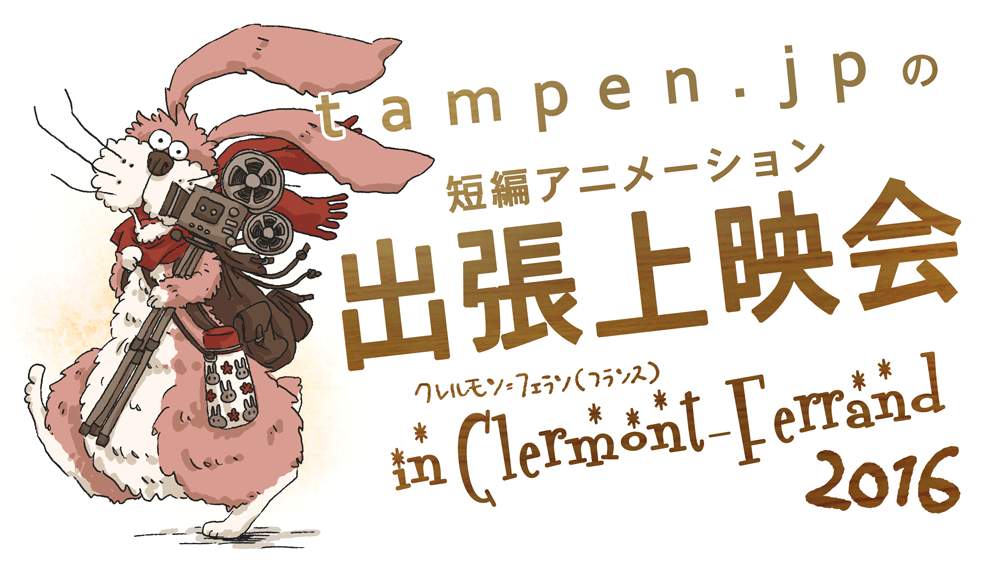新千歳空港国際アニメーション映画祭2018メインヴィジュアル:久野遥子
今年も新千歳空港国際アニメーション映画祭が、11月2日(金)から5日(月)まで新千歳空港ターミナルビルにて開催される。今年で5周年を迎える同映画祭は、世界中のすぐれた短編アニメーションの上映はもちろん、商業アニメの爆音上映や発声可能上映など、既存のアニメーション映画祭のイメージに囚われない多種多様なプログラムが特徴だ。今年からは長編コンペティションと学生コンペティションが新設されるということで、ますます注目を集めるだろう。しかし、アニメーション映画祭の目玉はやはり短編コンペティションだ。そこでtampen.jpでは、フェスティバル・ディレクターを務める土居伸彰氏に、短編コンペティションについてじっくりお話をうかがった。短編アニメーションはどうしても、難解でとっつきにくいという印象をもたれがちだ。しかし、土居氏のことばを借りれば「作品の声に耳を傾ける」ことで、難解さの先に豊かな世界が広がっていることを感じられるはずだ。そして、映画祭は「作品の声に耳を傾ける」のにもってこいの場なのだ。このインタヴューが「作品の声」を聴く手助けとなれば幸いである。(取材/構成=田中大裕)
土居伸彰/Nobuaki Doi
株式会社ニューディアー代表、新千歳空港国際アニメーション映画祭フェスティバル・ディレクター。ロシアの作家ユーリー・ノルシュテインを中心とした非商業・インディペンデント作家の研究をおこなうほか、世界のアニメーション作品を広く紹介する活動にも精力的にかかわる。著書に『個人的なハーモニー ノルシュテインと現代アニメーション論』、『21世紀のアニメーションがわかる本』(いずれもフィルムアート社)など。
新千歳空港国際アニメーション映画祭 公式サイトhttp://airport-anifes.jp/
ーーアニメーション映画祭において短編コンペティションというのは、ひとつの花形だと思います。まず前提として、新千歳空港国際アニメーション映画祭(以下、新千歳)では、短編コンペティションをどのように位置づけているのかおうかがいできればと思います。
土居伸彰(以下、土居) 短編コンペティションは、アニメーション映画祭のなかでも重要な位置を占めています。世界で最初のアニメーション映画祭として、1960年にアヌシー国際アニメーション映画祭(以下、アヌシー)がはじめて開催されて以来しばらくのあいだは、アニメーション映画祭=短編コンペティションという歴史があるわけですから。新千歳は作家性・世界観を重視する映画祭なので、それがもっとも濃厚にでる短編コンペは、僕がフェスティバル・ディレクターを務めるに以上、絶対に中心にしたかった。空港からも「コンペティションはぜひやってほしい」と後押しいただいたのですが、第一回の開催時には、正直、動員的には(ほかのプログラムと比較して)厳しいんじゃないかと思っていました。ですが、「映画祭の中心は短編コンペティションなんだ」という姿勢を示すためにも、会場でいちばん大きなスクリーンで(短編コンペティションを)上映することにしました。新千歳は人気アニメ作品なども含む多様なコンテンツを用意しているがゆえに、ともすれば(短編コンペティションが)埋もれてしまう可能性もありますが、きちんと重点を置きたかったのです。ありがたいことに、お客さんはたくさん入ってくれました。だから、最大のスクリーンを短編コンペティションに割りあてる方針は、変えずにやっていくつもりです。日本作品を対象とする日本コンペティションなども同様です。
ーー現在、世界中でアニメーション映画祭が開催されています。なかでも日本は、世界四大アニメーション映画祭に数えられる広島国際アニメーションフェスティバル(以下、広島)が長年、存在感を放っています。そうした状況のなかで、新千歳の短編コンペティションはどのようなプレゼンスをもっていると考えていますか。
土居 新千歳自体がまだ若い映画祭ということもあり、これからのアニメーション・シーンを担う新しい才能を積極的にピックアップしていくという方針があります。それが結果的に、広島との棲みわけにつながると考えています。広島との棲みわけという観点でもうひとついうと、開催国である日本の作家をきちんとピックアップする、ということです。アヌシーをはじめ多くの映画祭では、自国の作家をいかにピックアップするかを考えているんですね。開催国の作品を対象にした賞を用意したり。ところが広島は、日本作品があまりコンペティションに選ばれない。それについては賛否両論、議論がおこなわれていますが、ひとまず新千歳の方針としては、必ず一定数の日本作品がラインアップに入るようにしたいと考えています。そうした意味では、日本コンペティションや日本グランプリを別枠で設けることは(新千歳の方針として)重要であると考えています。なぜならば、日本の作家が国際的な舞台に飛び立っていくための足がかりに(新千歳が)なってほしいと願っているからです。また、国際的にも影響力のある審査員に、最新の日本作品をジャッジしてもらう機会をきちんと用意するという意味でも、日本コンペティションは重要であると考えています。日本の新しい才能を「発見」して、拾いあげてほしいのです。
ーー新しい才能の発掘に重心をおいているというお話でしたが、新千歳は他方で、たとえばBoris Labbé監督のようオーセンティックな作家に関しても、きちんと継続的に評価していますよね。土居さんはしばしば、短編アニメーションの「伝統」がみえづらくなっているという趣旨の発言もしていますが、新千歳における「伝統」の位置づけをどのように考えていますか。
土居 まず「なにがオーセンティックか」という、そもそもの了解がとりづらい時代になっていると思うんですね。Boris Labbéをオーセンティックな作家といわれましたが、ではそのような文脈が、日本でアニメーションにかかわっている人間のあいだでどれだけ共有されているのか。ここでいうオーセンティックとは、アヌシーや広島を中心に築きあげられた伝統的な価値観を継承している作家という意味ですがーー僕は必ずしも、それが本当の意味でオーセンティックとは考えていませんがーー、いまはひとくちに短編アニメーションといっても、さまざまな文脈で作品がつくられています。そうした状況のなかで、誰が「伝統」を引き継いでいて誰が「伝統」の外側から入り込んできたのか、という見取り図が把握しづらくなっている。そこで新千歳の方針としては、むしろいろいろな文脈を混ぜてやろうと思っています。新千歳の短編コンペティションは、世界の短編アニメーション・シーンの縮図となるようなセレクションをめざしています。そのなかには「オーセンティックな」文脈もあれば、それとは違う文脈もある。
Boris Labbé『The Fall』
ーー新千歳の短編コンペティションのおもしろいところは、映画祭文脈の「伝統」を引き継いだオーセンティックな作家と、たとえばDon Hertzfeldt監督のような「伝統」の外側から飛来した作家をぶつけるようなキュレーションだと思います。そうしたキュレーションの意図も、短編アニメーション・シーンの縮図をめざしているからですか。
土居 そうですね。ただDon Hertzfeldtは、アニメーション映画祭の文脈においても、すでに浸透した存在になりました。いまの関心はむしろ、「映画の文脈でつくられているわけではないが、映画館のスクリーンで上映したらおもしろい」という位置づけのものにあります。今年は中国作品を多く選んでいるのですが、その理由は中国には現代美術の分野で活躍しているアニメーション作家がたくさんいることを示したかったからなんです。中国ではいま、アート・ギャラリーがアニメーションの主戦場として存在感を高めている。ギャラリーを主戦場とする作家にとって、アニメーションは原画を売るためのプロモーションの手段という側面はあるのですが、とはいえコンセプト的にも技術的にもすぐれた作品がたくさんある。今年のラインアップのなかではSun Xun、あとは日本ではまだほとんど知られていない作家だと思うのですがLiu Yiはまさにです。今年は、そうした新しい流れと伝統的な映画の文脈がぶつかることで、すごくおもしろいことになっていると思いますね。
Don Hertzfeld『World of Tomorrow Episode Two: The Burden of Other People’s Thoughts』
ーー国別のアニメーション制作数を考えると、ドイツもかなり健闘しているように思いました。
土居 ドイツは、フランスと並んで短編アニメーションをつくりやすいシステムが成熟している国なので、層は厚いですね。そのなかでも、オーセンティックなアニメーションの文脈からは外れたところでがんばっている作家というとDavid Buobです。もともとはインスタレーションなどを制作していたのですが、『Das Haus』(2011年)という大傑作で鮮烈な映画祭デヴューを飾った作家です。今回は『The Big Rip』(2018年)という作品がノミネートしていますが、この作品は今年の注目作品のひとつですね。ドイツの作家でいえばJochen Kuhnも注目です。日本ではちゃんと紹介されていない作家ですが、彼もやはり、現代美術とアニメーション映画の境界に立つ作家で、ナレーションによって紡がれるアイロニカルな物語と、ペインティングの伝統を引き継いだヴィジュアルが特徴です。彼のアニメーションは、「動く絵画」としての美学を重視していて、それゆえに一般的なアニメーションと比較すると動いていないように感じられるかもしれませんが、短編映像のもつ独特な時間性という観点では、かなりおもしろい試みをしている作家です。世界四大アニメーション映画祭のなかでもとりわけ、実験映画の文脈が色濃いザグレブ国際アニメーション映画祭(以下、ザグレブ)ではすでに注目されていた作家で、日本での認知度はまだまだ低いですが、興味深い作品をたくさんつくっているのでぜひ注目してほしいですね。
David Buob『THE BIG RIP』
ーー実験映画とのかかわりでいうと、実写素材を大胆に使用した『RERUNS』(Rosto、2018年)は、スチルをみただけでもインパクトばつぐんですね。
土居 Rostoは実写素材+精密な3DCGという組み合わせをずっと追求している作家ですね。Rostoも伝統的なアニメーション映画祭の文脈では評価されづらい作家です。それにRostoの作品は、「Rostoワールド」の断片というような趣もあって、作品単体でみるとわかりづらいところもあるんです。フィルモグラフィーをとおしてみることではじめて理解できるようになる部分もある。しかしだからこそ、新千歳でRostoを継続的にとりあげることは使命であると考えています。数年間かけて継続的にRosto作品の鑑賞履歴が重なっていくことにより、「そういうことか」とわかっていただければなと。新千歳では、作家それぞれが固有の方法論に辿りついているーーある種の島宇宙的な事例は積極的に紹介する方針を打ちだしているので、それぞれの作家に見合った紹介のしかたをつねに考えていきたいです。
Rosto『RERUNS』
ーーそうした方針もあってか、新千歳の短編コンペティションは毎年、驚くほど手法がバラバラですよね。
土居 それは、手法であったり物語の語りかたがかぶらないように意識しているからでもあります。すぐれた作品であっても、選考段階で表現上のかぶりを避けるために、涙を吞んでコンペティションに入れない選択をすることもめずらしくありません。多様性をキープすることを映画祭の方針としてそれだけ重視しているということです。なので、オーソドックスに物語を語る作品を選ぶ一方で、物語ることにまったく関心がないような作品も選んでいます。
後半へつづく