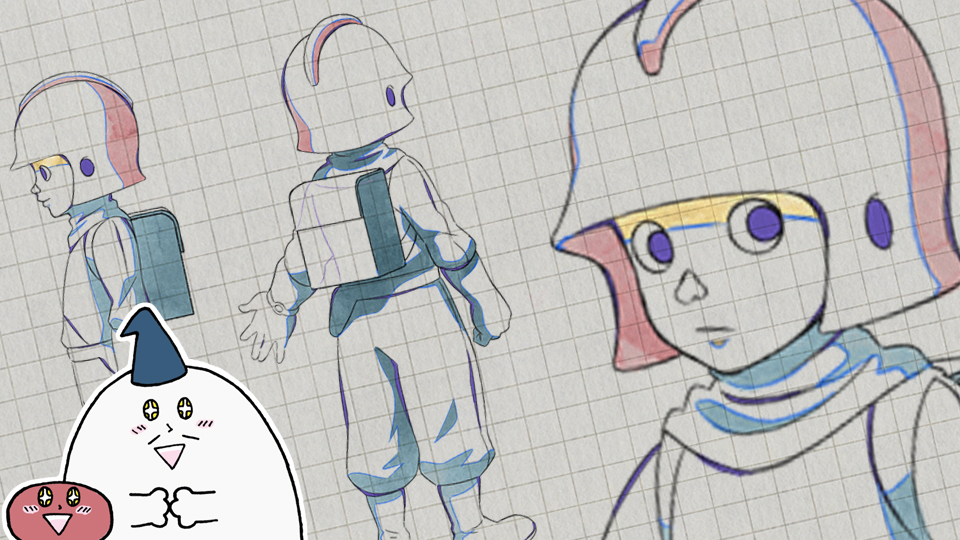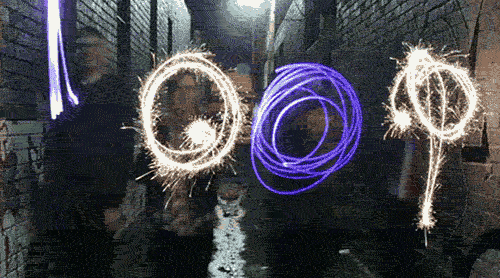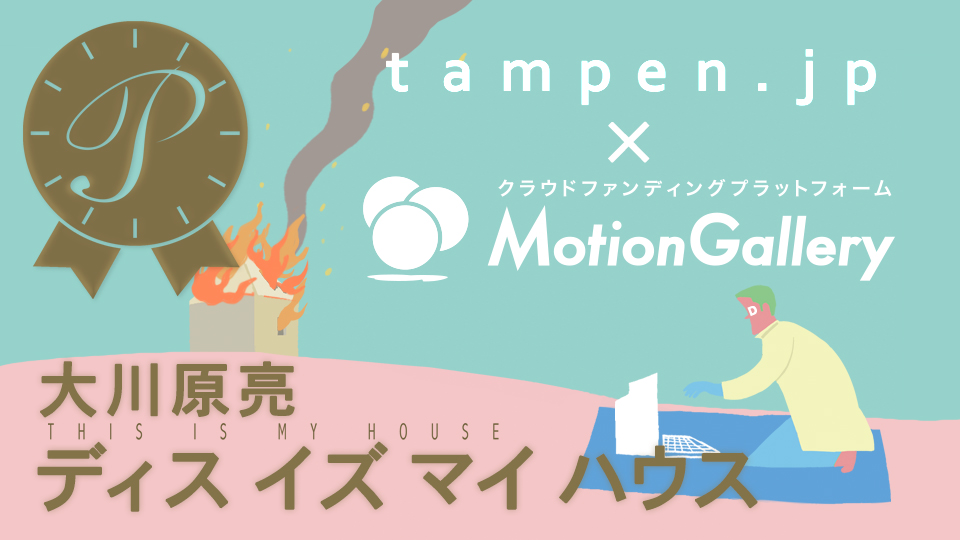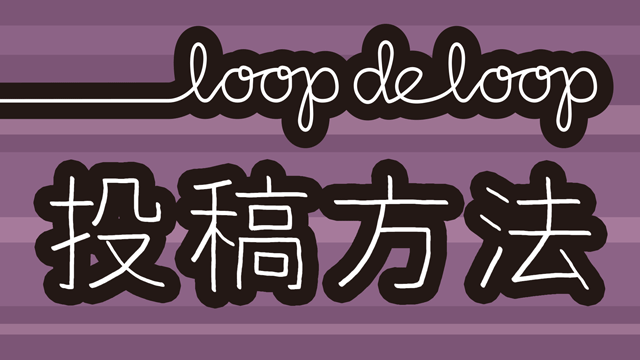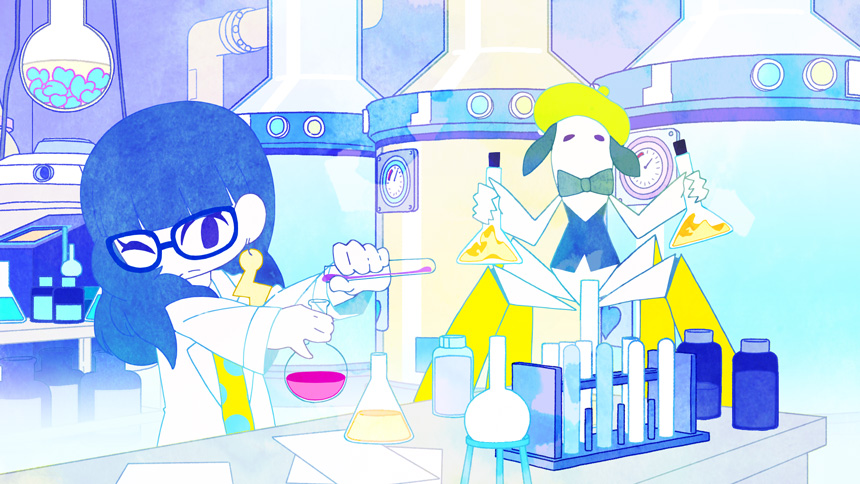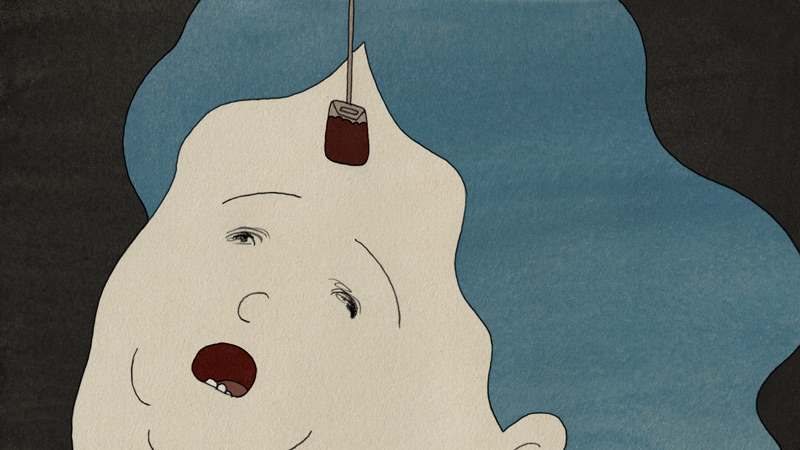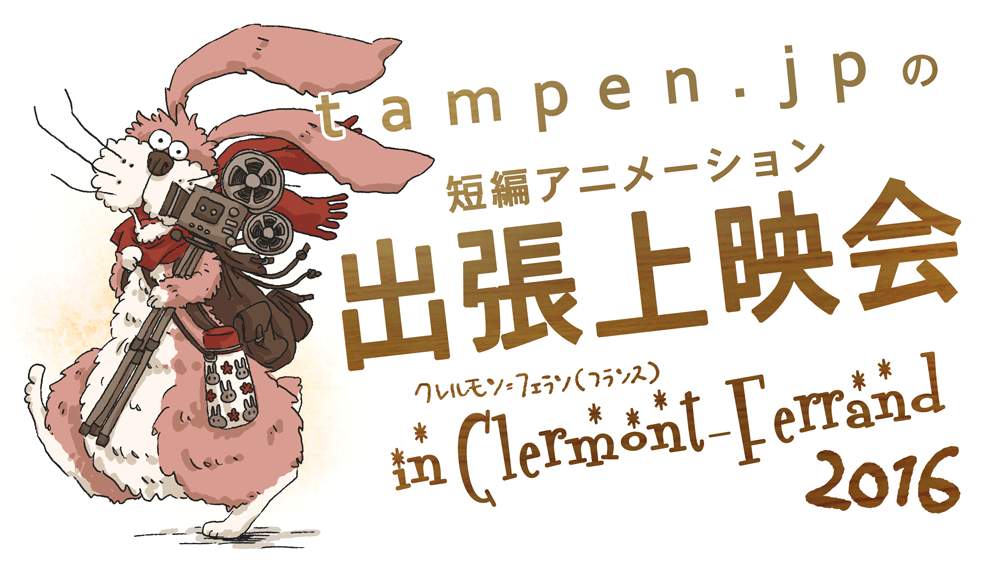第5回新千歳空港国際アニメーション映画祭メインビジュアル:久野遥子
2018年11月2日から5日、北海道にて第5回新千歳空港国際アニメーション映画祭(以下、新千歳)が開催された。本稿では、そのなかでも短編コンペティションを中心にレポートしたい。同映画祭フェスティバル・ディレクターの土居伸彰は、過去のインタビューのなかで新千歳について、複数の文脈を絡み合わせることでアニメーション・シーンの縮図を見せたいと語っていた(関連記事:新千歳空港国際アニメーション映画祭フェスティバル・ディレクター 土居伸彰氏インタヴュー <前半>)。であるならば、そのレポートとは、複数の文脈が交わるゆいめに瞳を凝らすものであるべきだろう。それゆえに本稿は、なるべく多くの作品を横断するように(ときには立ち戻りつつ)展開していくことになる。また、限られた紙幅のなかですべての作品に触れることはできないことをあらかじめ断っておく。なお、今年の新千歳はきわめて高水準であり、本稿で触れられなかった作品のなかにもすばらしい作品が揃っていたことは言い添えておきたい。それではさっそく作品について見ていこう。
まずは、アニメーション映画祭の花形である短編コンペティションでグランプリに輝いたRéka Bucsi『Solar Walk』(2018年)だ。Bucsiは、代表作『Symphony no. 42』(2014年)がアカデミー賞をはじめ世界中の映画祭でノミネート/受賞するなど、すでに国際的な評価を盤石にしている作家だが、筆者の印象としては、『Solar Walk』が現時点でのキャリアハイと言っても過言ではないだろう。
Réka Bucsi『Solar Walk』
まるで原子運動のような宇宙旅行や、フェンリル(北欧神話に登場する狼の怪物)のような生物の排泄物が宇宙を創造するなど、『Solar Walk』では小さな営みと宇宙的なスケールのできごとが絶えずひっくり返りながら循環していく。グランプリ受賞理由のコメントが、『Solar Walk』の美点を端的に言いあらわしているので引用したい。
おそらくこの世界は、ユニバース(単一の宇宙)というよりはマルチバース。かたち、色、音が舞う、魔法のような世界。(中略)あらゆる出来事が、平穏さ、喜び、強烈な優しさと共に起こります。あらゆるものが、それよりも大きな何かの一部です。時間も空間も、この世界では、固有のロジックとダイナミズムを持っています。(映画祭公式サイトより引用)
『Solar Walk』では、小さな原子から巨大な宇宙まで、異なるスケールが渾然一体となってひとつの世界をつくりあげている。さらに、異なるスケールの事物を結びつけるメディウムとして、音楽が効果的に使用されている点は見逃せない(もしくは聴き逃せない)。宇宙の原理を音楽が体現しているという思想自体は伝統的なものだ。たとえば、宇宙全体がハーモニーを奏でているという発想ーーいわゆる「天球の音楽」はよく知られているだろう。いずれにせよ『Solar Walk』において、音楽はきわめて重要な役割を担っている(余談だが『Solar Walk』はもともと、オーケストラコンサート用に制作した映像を短編映画につくりなおしたものだそうだ)。ここで注意を払うべきは、『Solar Walk』が上映されたのと同じ日に、『リズと青い鳥』(山田尚子、2018年)と『秒速5センチメートル』(新海誠、2007年)も招待作品として上映されている点だ。どちらの作品もミクロな人間関係のうちに世界のすべてに触れてしまうような神秘的な経験を描いており、なおかつその手段として音楽が重要な役割を担っているという意味において、『Solar Walk』とよく似ている。ちなみに当日は、『リズと青い鳥』→『秒速5センチメートル』→『Solar Walk』という順番で鑑賞できるように、プログラムが組まれていた。じっさい筆者も、あいだに別のプログラムを挟みながら、その順番で鑑賞している。この順番というのは、大規模な集団制作作品(『リズと青い鳥』)→それよりはやや規模の小さなインディペンデント作品(『秒速5センチメートル』)→個人制作作品(『Solar Walk』)という流れになっており、おそらくかなり意図的に配置されている。つまり、異なる文脈でつくられた作品であっても世界観を共有しているということが、映画祭をとおして照らしだされるかたちだ。
山田尚子『リズと青い鳥』
新海誠『秒速5センチメートル』
そうした意味では、日本グランプリに輝いた和田淳『秋 アントニオ・ヴィヴァルディ「四季」より』(以下、『秋』)も、一連の流れの延長線上に位置づけることが、あるいは可能かもしれない。
和田淳『秋 アントニオ・ヴィヴァルディ「四季」より』
和田のアニメーションのなかでは、登場キャラクターは他者とのコミュニケーションにしばしば失敗する。しかし失敗して終わりではなく、ズレを含んだ歪な関係が、そこでは育まれる。そうしたコミュニケーションのズレが連鎖していくことで、さまざまな存在がほつれながらもゆるゆるとネットワークされていく。それはコミュニケーションの不全という意味において孤独を描いているように思えるが、同時に、それでもなお私たちはどうしようもなく世界の一部である、ということを諧謔的に描いているようにも思える。もっとも、それは冷笑的ということではない。むしろ、どこか慈しみにも似たやさしいまなざしが感じられる。そうした懐の深さこそが、和田の美点であろう。そうした美点は、『秋』においてさらに深化している。
また、和田は同映画祭にもうひとつ作品を出品していた。それは2019年ローンチ予定のゲーム『マイ エクササイズ』だ。近年インディーゲームは、アニメーション作家が作家性をキープしたままマネタイズする方法として注目されている。2017年にはDavid Oreilly『Everything』(2017年)のトレーラーが、複数のアニメーション映画祭で受賞するなど、いまやアニメーションの領域においてもゲームはきわめて重要な位置づけにあると言えよう。新千歳空港国際アニメーション映画祭も第4回では、ゲームを大々的にフューチャーしている。今回も、国際審査員のひとりで美術家の谷口暁彦によるゲームアートに関するレクチャーや、試遊展示がおこなわれた。『マイ エクササイズ』も試遊展示にラインアップされていた。筆者はスケジュールの関係で残念ながら、『マイ エクササイズ』をプレイすることは叶わなかったが、別の機会に和田による『マイ エクササイズ』のプレゼンテーションを観覧している。『マイ エクササイズ』は、スペースキーを押す(スマートフォン版はタッチする)ことで画面上の男の子が腹筋をするという、とてもシンプルなゲームだ。腹筋の回数に応じて、男の子の周囲に動物が集まってきたり、画面上になんらかの変化が生じる。まだローンチされていないタイトルなのでネタバレは避けるが、腹筋をくり返すことで驚くべき展開が待っている。筆者の見立てでは、『マイ エクササイズ』は『秋』と対になるような作品に思われた。いまから来年のローンチにむけて期待が高まる。
和田淳『マイ エクササイズ』
アニメーション映画祭においてゲームが存在感を増していることは、すでに確認したとおりだが、あるいはゲーム以上にアニメーション映画と長らく結びついてきたのが、メディアアートだろう。もっとも、映画とメディアアートの線引きは、それほど自明ではない。いずれにせよ、今年の新千歳では、映画館や自宅のディスプレイで鑑賞することを前提としていない作品や、一般的な映画鑑賞とは異なるしかたで鑑賞することを要求してくる作品が、いくつか上映された。そのなかでも筆者がとりわけ印象的だったのは、『The Earthly Men』(Liu Yi、2017年)と『何処かへ。』(高橋良太、2018年)だ。
『The Earthly Men』は、中国の伝承のなかで語られる、白水郎の物語をベースにしている。白水郎とは、白水にいたという潜水の得意な男の呼び名であり、転じて漁師を意味することばになった。つまり白水郎は、匿名的な個人が、匿名的であるがゆえに集団的なものの流入を許し、誰でもあって誰でもない存在になったということだ。『The Earthly Men』は、そんな白水郎を個人という枠組みがあいまいになった現代社会の在りようと重ね、水墨画を素材とした流動的なアニメーションで表現している。『The Earthly Men』を見た観客が、おそらくまっさきに驚くのは、縦長の画面だろう。『The Earthly Men』はもともと、ギャラリーで展示されていた作品のようだ。作者によると縦長の画面は、スマートフォンの画面を意識したという。『The Earthly Men』はおそらく、ネット社会がもたらす個人の均質化を批評的な視点から描いているのだろう。
Liu Yi『The Earthly Men』
『何処かへ。』もまた、匿名性や均質性について描いている。『何処かへ。』の冒頭では、撮影およびSNSでシェアすることを許可するクレジットが挿入される。その意味は作品を最後までみることで理解されるだろう。『何処かへ。』にはキャラクターがいっさい登場しない。「温かみ」を徹底的に排除した質感の3DCGによって描画された教室が、どこまでもつづいていくばかりだ。「温かみ」を欠いた均質で匿名的な世界から抜けだせない息苦しさは、学校空間に代表される集団的な「空気」の暴力性を想起させる。しかし最後に、黒板に書かれた巨大なQRコードが映しだされる。QRコードを読み込んだ先では、作者からの手紙を読むことができる。ネタバレに配慮して詳細は伏せるが、その手紙の内容とは、作者がみずからの不登校経験を振り返り、「つらいときには逃げだしてもよい」と語りかけるものだ。したがって、『何処かへ。』でカタルシスに到達するためには、ただ受動的に映画を眺めるだけでは不十分で、QRコードを読み取るという能動的な行動が必要になる。つまり、『何処かへ。』の主人公は、観客一人ひとりと言えるかもしれない。なぜならば『何処かへ。』には、ただ見ているだけで観客のかわりに困難を乗り越えてくれるような主人公は存在しないのだから。
高橋良太『何処かへ。』
さて、『リズと青い鳥』『秒速5センチメートル』にいったん立ち戻ってみよう。『リズと青い鳥』『秒速5センチメートル』からの連想という意味においては、『Bloeistraat 11』(Nienke Deutz、2018年)『タンポポとリボン』(若井麻奈実、2018年)にも光を当てたい。いずれの作品も、閉じられた親密な関係性が、他者(や世界の法則)の介入によって、不可避的に変化していく様子を丹念に描いている点が共通する。さらに興味深いのは、『Bloeistraat 11』と『タンポポとリボン』において、介入者によって変化する関係性を描くうえで、素材の性質や「モノ」としての在りようが反映されている点だ。
『Bloeistraat 11』では、思春期の少女たちの密やかな関係性が他者の介入によって変化していく様子を、不可避の身体的変化と重ねて描く。そこで『Bloeistraat 11』においては、キャラクターを描く支持体として、透明なアクリル板が選択されている。透明な素材は、少女たちが同化することを許すと同時に、外界からつねに影響されることも意味する。思春期の揺れ動く不安定なアイデンティティーを、素材の性質を利用して巧みに表現する『Bloeistraat 11』は、物語と手法が分離不可能に結びついた好例と言えよう。なお、『Bloeistraat 11』は新人賞を受賞している。
Nienke Deutz『Bloeistraat 11』
審査員特別賞とロイズ賞に輝いた『タンポポとリボン』は、擬人化されたタンポポとリボンの関係性の変化を丁寧に描く。ふたりには、リボンがみずからの身体をほどいてタンポポが結びなおす、という密かな遊びがある。やがて、「モノ」として在りようの違いが、ふたりの関係性に変化を生じさせる。『タンポポとリボン』を素朴に人間関係のアレゴリーとして読むことは可能だが、それにとどまらず、異なる属性をもつ事物一般の関係を代入可能な懐の深さこそが、『タンポポとリボン』の白眉であろう。それを可能たらしめているのは、『タンポポとリボン』の構成が、徹底してふたりの関係にのみフォーカスを絞り、ひとつのシチュエーションを反復する、きわめてミニマルなものだからだろう。もっとも、なんでも代入できてしまうということは逆説的に、「それそのもの」のかけがえのなさをかえって際立たせることになる。観客が『タンポポとリボン』の物語になにを仮託するも自由だが、そんなことはおかまいなしにタンポポとリボンは、かけがえのない固有の関係性を育んでいく。そこに『タンポポとリボン』の尊さがある。余談だが筆者は、新千歳以前にすでに『タンポポとリボン』を鑑賞している。しかし白状すれば、初見で『タンポポとリボン』の豊かなポテンシャルに気がつくことができなかった。裏を返せば、映画祭をとおしてポテンシャルに気がつけたということであり、各作品のポテンシャル引きだすキュレーションがおこなわれていたという証左であろう。
若井麻奈実『タンポポとリボン』
さて、ここまでとりあげてきた作品にゆるやかに通底するのは、どの作品も作品独自のロジックや世界観を明確に打ちだしているということだろう(すぐれた作品であればあたりまえだろうが)。そうした観点から最後にひとつ紹介しておきたいのが『Geenie Reenie』(Andrew Onorato、2017年)だ。今年の新千歳において、筆者がもっとも衝撃を受けたのが『Geenie Reenie』だ。『Geenie Reenie』は、ハニワのような外見ををした幽霊のような生物たち(もはや生物であるかどうかすらも疑わしいが)の奇妙としか形容不可能な生活の様子を描く。百聞は一見にしかず。まずは本編を見てほしい。
Andrew Onorato 『Geenie Reenie』
おそらく観客の誰しもが、意味がわからないと思ったのではなかろうか。筆者もそのような感想をもった。主人公がスパムに引っかかるなど、わかりやすいネタがところどころに散りばめられてはいるものの、そのはるか手前で意味がわからないのだ。なんらかのアレゴリーである可能性も捨てきれないが、ここまで意味不明だと強引に解釈することすらも困難だ。しかし、では無意味かと言われると、そうではないと断言できる。まったく意味はわからないのはたしかだが、他方で彼らがなんらかの慣習に則って行動していることだけは、はっきりと伝わってくる。それがどのような法則性なのかまるでわからないだけだ。しかし、では私たちが慣習にしたがって行動している様子を部外者が観察したとき、それが奇妙なものとして映らない保証はどこにもない。そう考えると彼らと私たちのあいだには、それほど違いはないのかもしれない。むしろ、彼らからすれば、私たちのほうこそ奇妙に映るかもしれない。そんなことを考えながら『Geenie Reenie』を見ていると、異なる存在をただありのまま受け入れる準備が整う感覚をおぼえないだろうか? なにしろ、まるで理解できないが、彼らはとても幸せそうに見える。
さて、本稿で紹介したのはプログラムのごく一部にすぎないが、新千歳において、商業/非-商業や映画/インタラクティヴ・アートといった垣根を越えてグルーヴが生みだされていたことがよくわかってもらえただろう。個々の作品を越えた映画祭全体でのグルーヴという意味においては、過去の同映画祭と比較しても、今年がいちばんであったように思う。個別の作品から共通性を浮かびあがらせるというのは、ともすれば個々の作品が置かれた文脈を軽視しているように思われるかもしれないが、むろんそうではない。むしろ、その正反対と言ってもよい。なぜならば、個別の作品から共通性を照らしだすことはひるがえって、個々の作品の差異を逆照射することにもなるからだ。個々の作品が置かれた近さと遠さをあらためて測りなおすことによって、個別的な鑑賞経験の積み重ねのもとには見えてこない、アニメーションという大海原の海図を手にすることができるだろう。すると、見慣れたアニメーションにたいしても、いままでとは違った彩りを再発見できるはずだ。それはまさしく、土居が語った「アニメーション・シーンの縮図を見せる」ことの意義だろうし、国内では(もしかすると世界的にみても)新千歳にしかできないことだ(今後、新千歳以外にも現れることを期待する)。だからこそ、新千歳の今後にますます期待が高まる。
新千歳空港国際アニメーション映画祭 公式サイト:http://airport-anifes.jp/
tampen.jpでは、新千歳空港国際アニメーション映画祭の関係者をゲストにお招きして、同映画祭の5年間の歩みとこれからについて語っていただくイベントを開催いたします! みなさまぜひ、ふるってご参加ください! イベント詳細は下記サイトにてご確認お願いいたします。
千歳空港国際アニメーション映画祭5周年記念トークイベン:https://t.co/0TBmGwFrIG